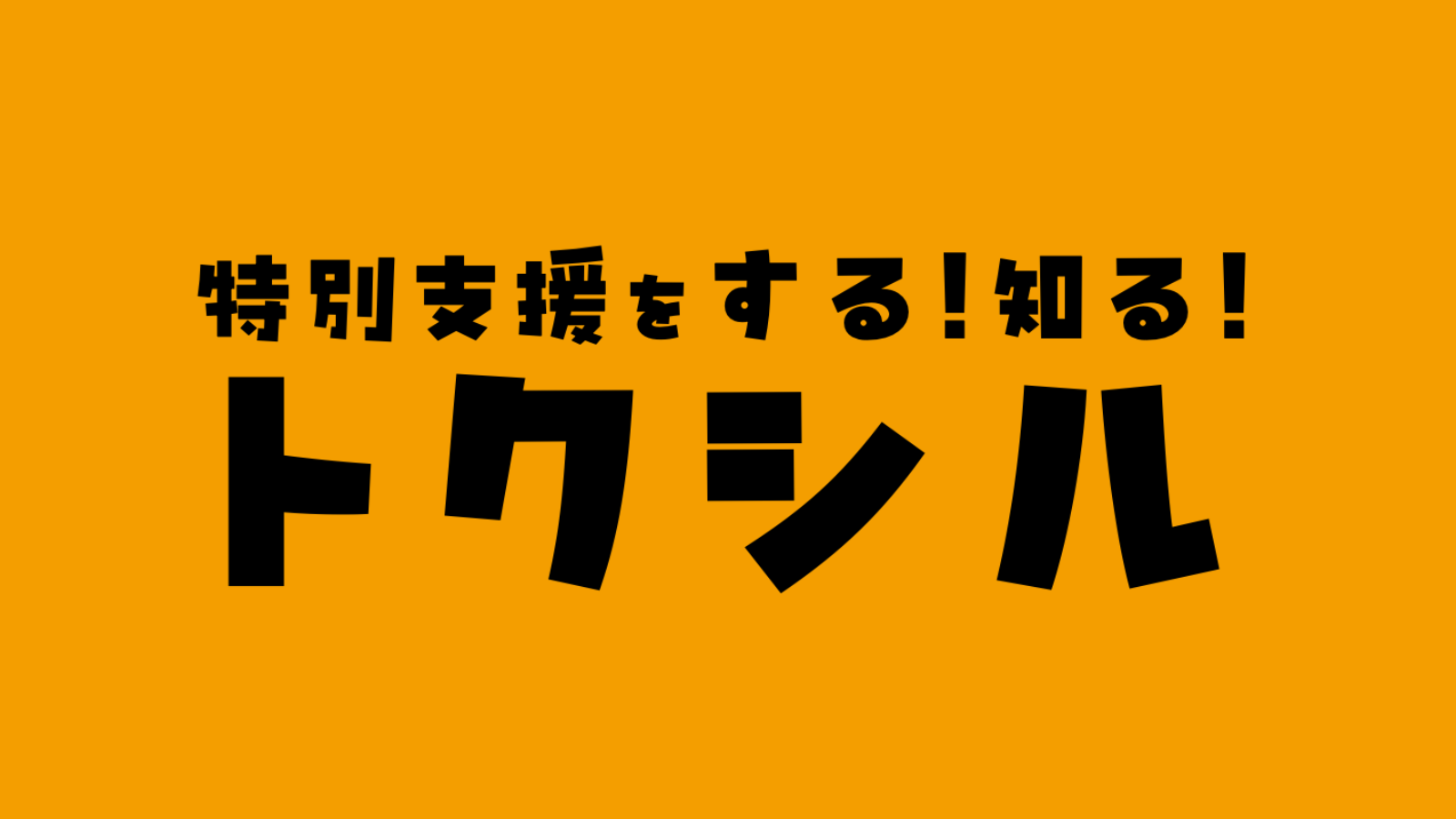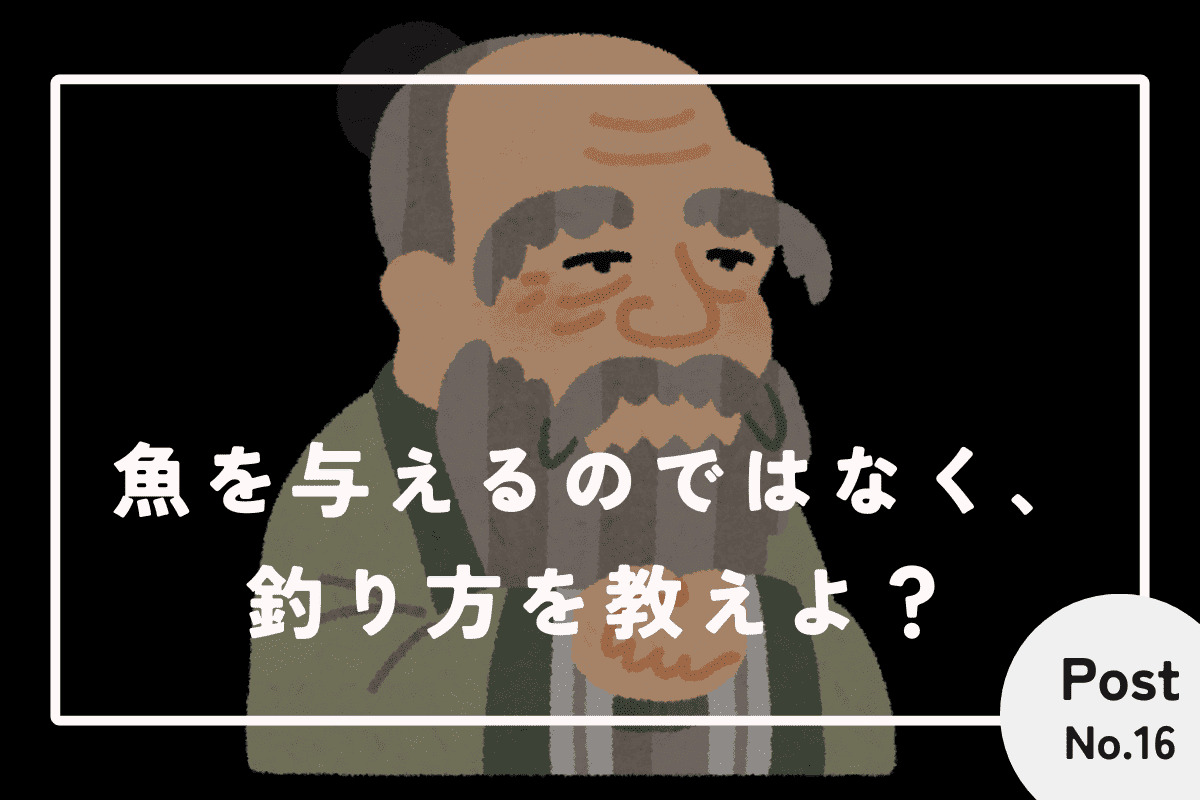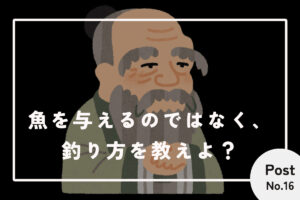ふと言われた一言

「特別支援学校の先生は、よくそんな踏み込んだ指導ができますねー」
ある先生がトクシルの支援に対して口にした言葉。トクシルの支援がやりすぎなのか?と思ったけど、そうではないみたい。



「人の人生に、よくそこまで責任もてるなーと…」
うーん。この人よく教師やってるな…と思いましたが、それはさておき。
「支援の出口戦略」と「自立を踏まえたときの支援の構造」がないと、こういった考え方に陥りやすいなと考えました。
これはブログ化した方が良い!と思い、年末年始にブログ化しております(笑)
支援の出口戦略
たとえば、漢字の読解が苦手な人への支援として、
漢字にルビを振る
これも一つの支援ですが、違った角度から考えると、
Googleレンズの使い方を練習する(漢字を撮影すると、読み方がでる)
「この漢字の読み方を教えてください」等の質問方法を練習する
という支援もあるかなと。
老子の有名な言葉に「魚を与えるのではなく、釣り方を教えよ」があります。人に魚を与えれば一日で食べてしまうが、釣り方を教えれば一生食べていけるという意味です。これと同じ。


例にあてはめると、「ルビを振れば、その漢字を容易く読めるが、Googleレンズの使い方を練習すれば、この先どんな漢字でも読める可能性が高まる。」といったところ。
と、ここまでは、よくある話ですが、ここから本題です。
じゃあ、魚を与えるのは間違い?
では、支援の出口戦略を考えると、漢字にルビを振ること(魚を与えること)は不適切な支援?でしょうか。
答えはNOです。
結論は、それらのつながりを意識して支援する=自立の観点を踏まえるということだと思います。トクシルの考える自立を踏まえた支援とその支援を受ける人の気持ちはこんな感じでしょうか。
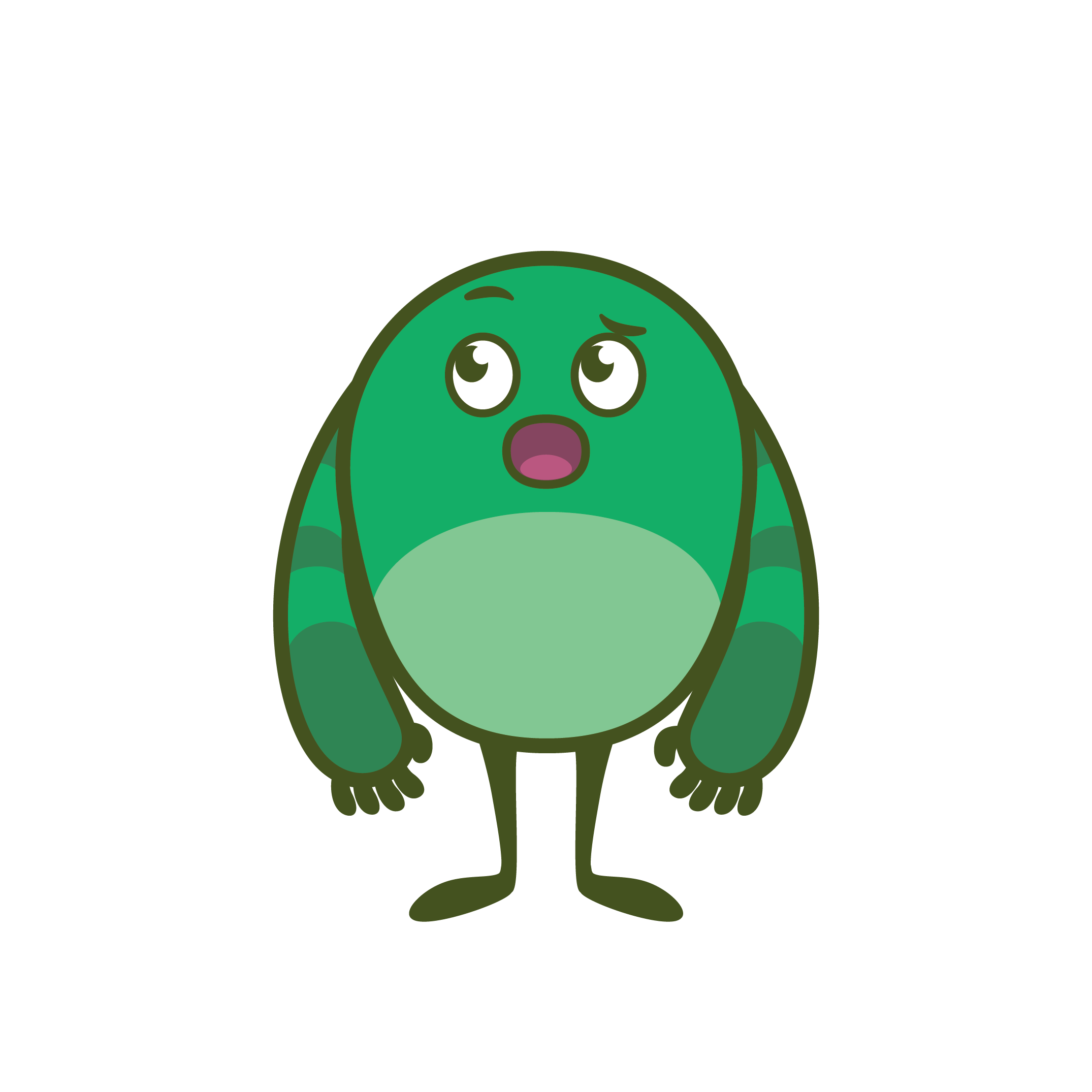
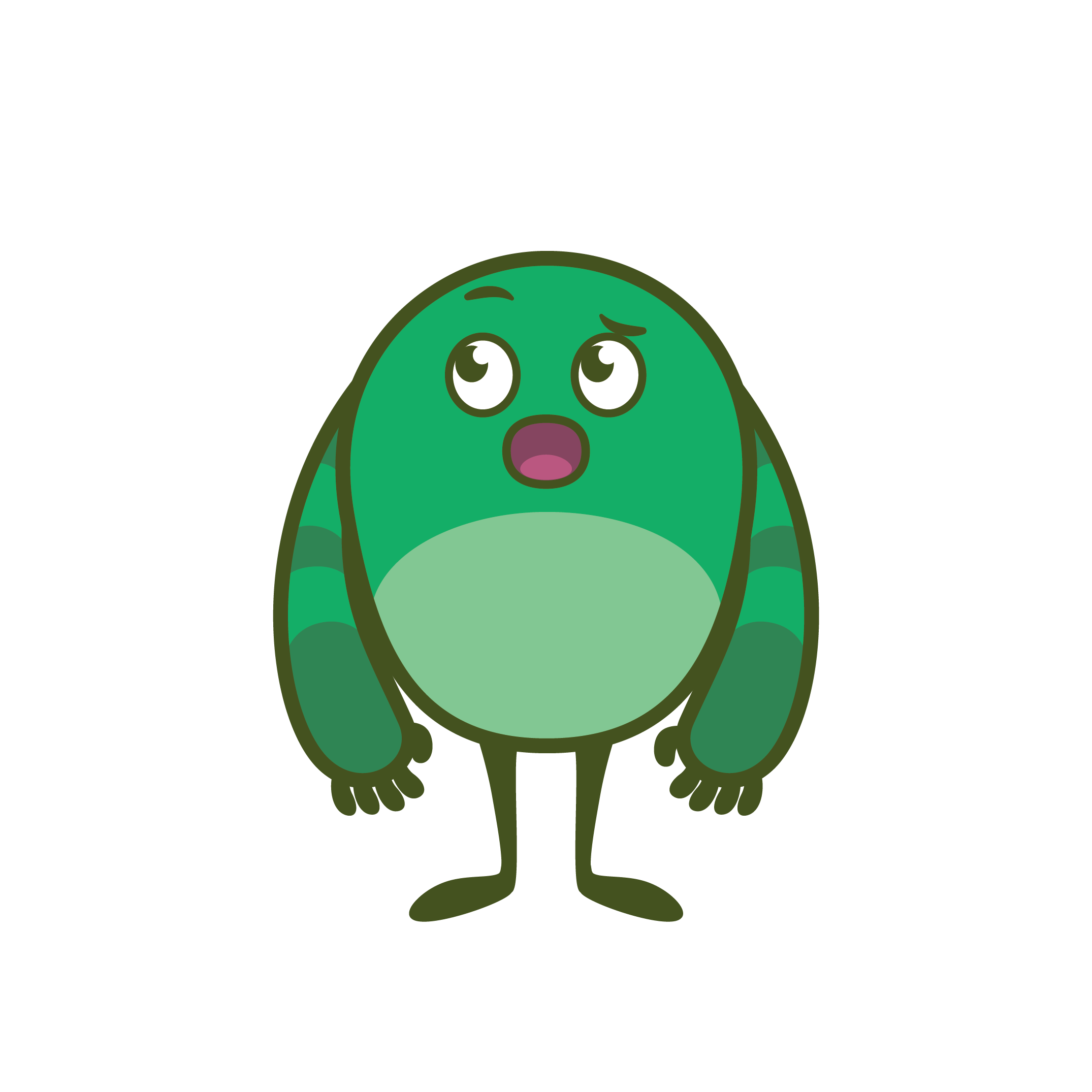
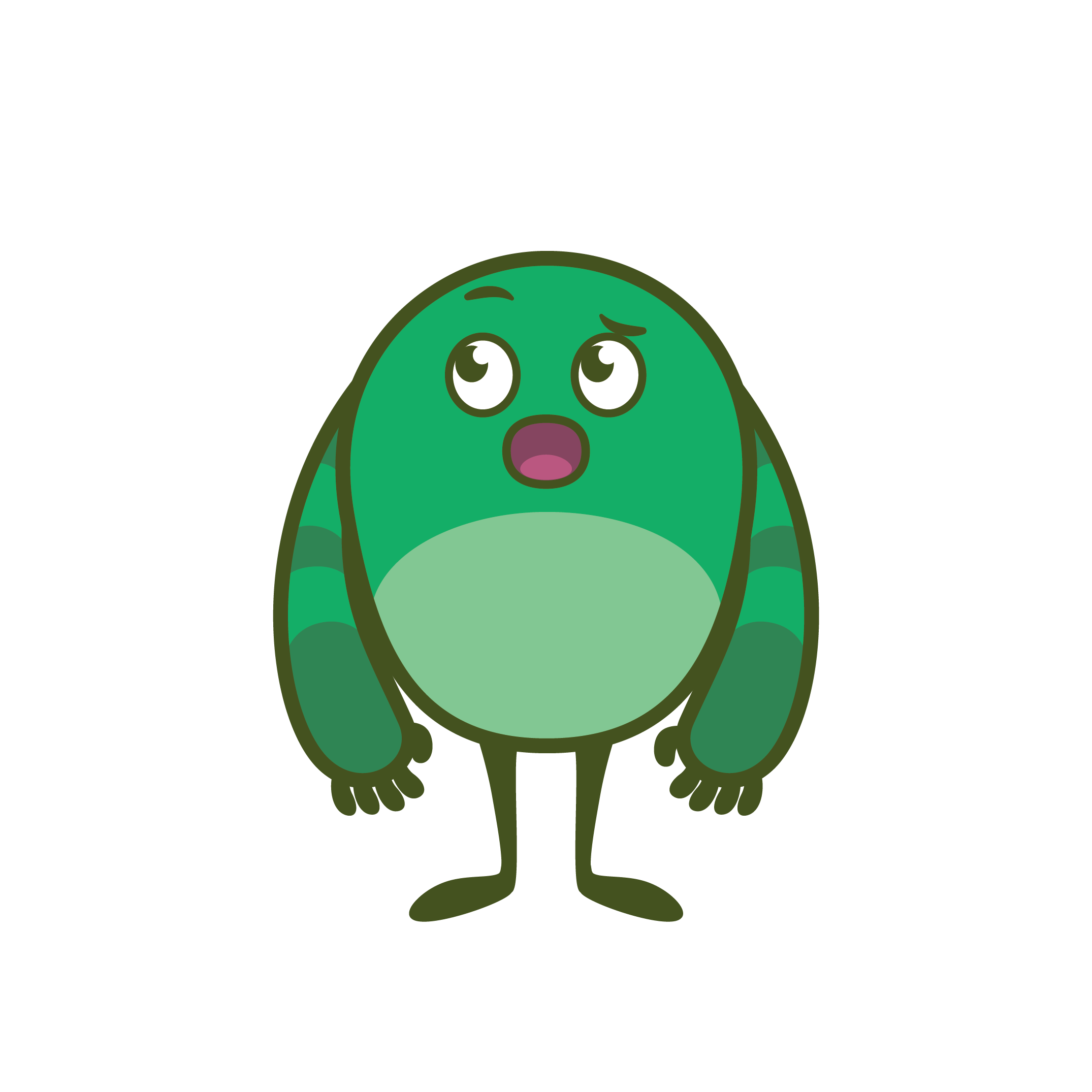
「ぜんぜん、よめません」
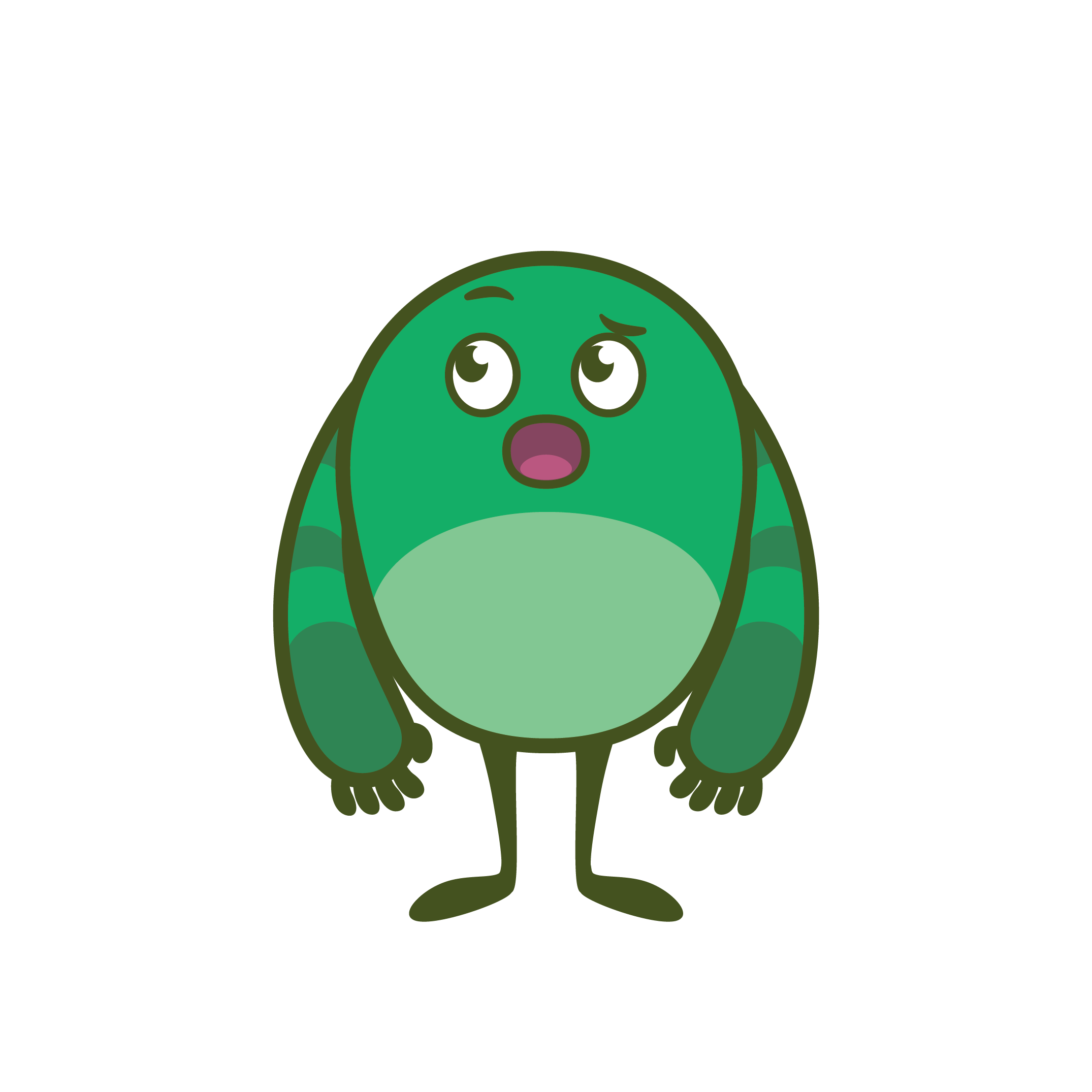
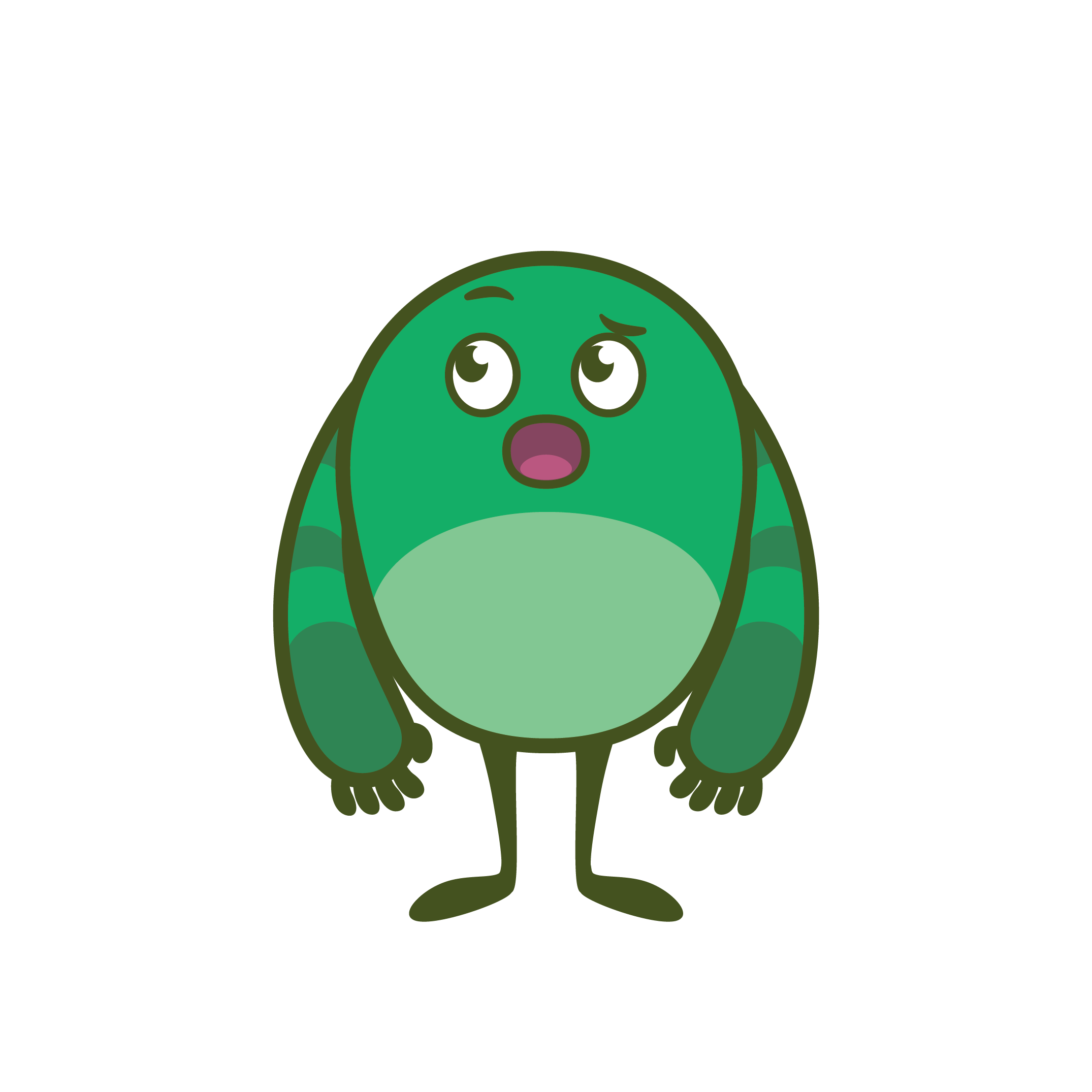
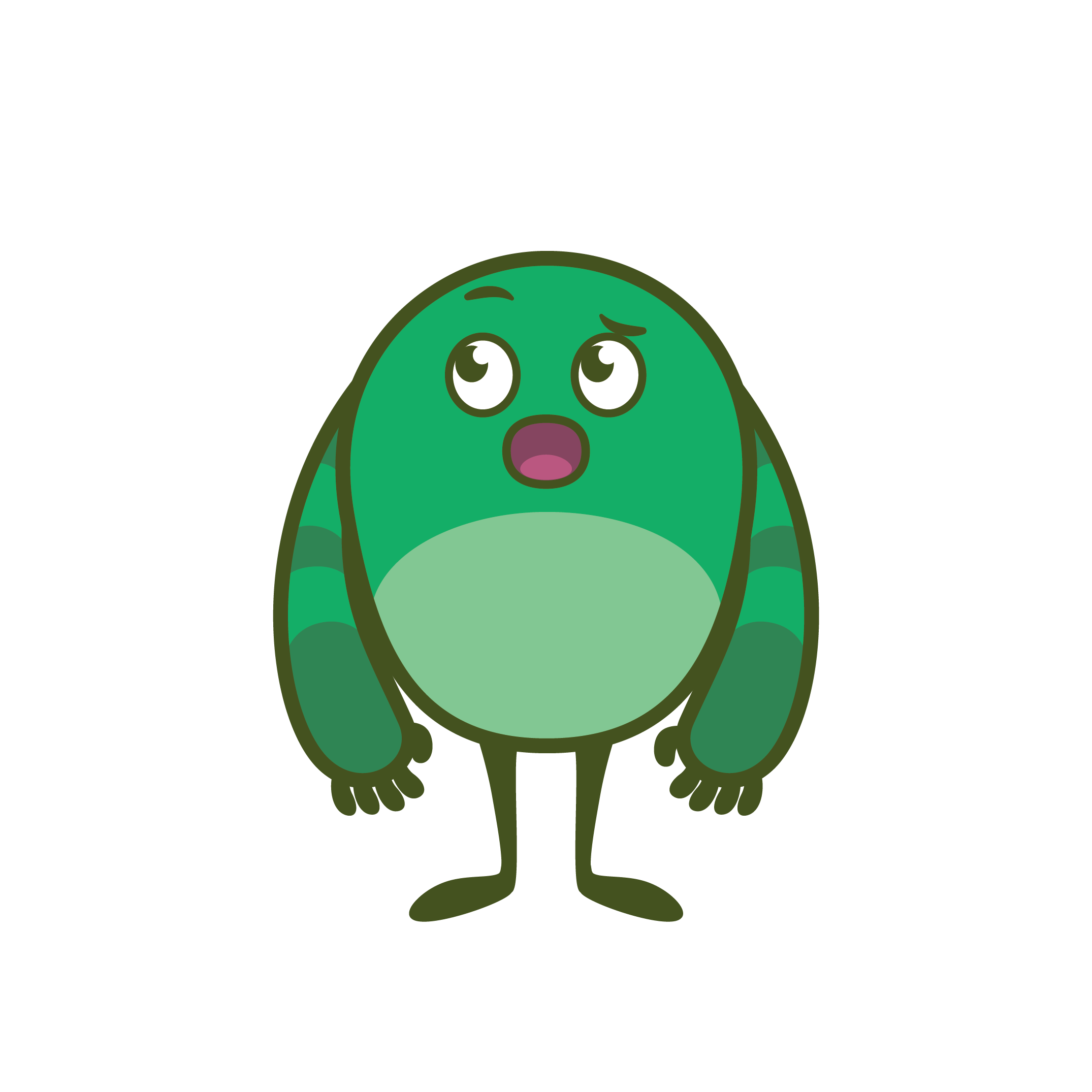
「なるほど、そういう内容ねー」
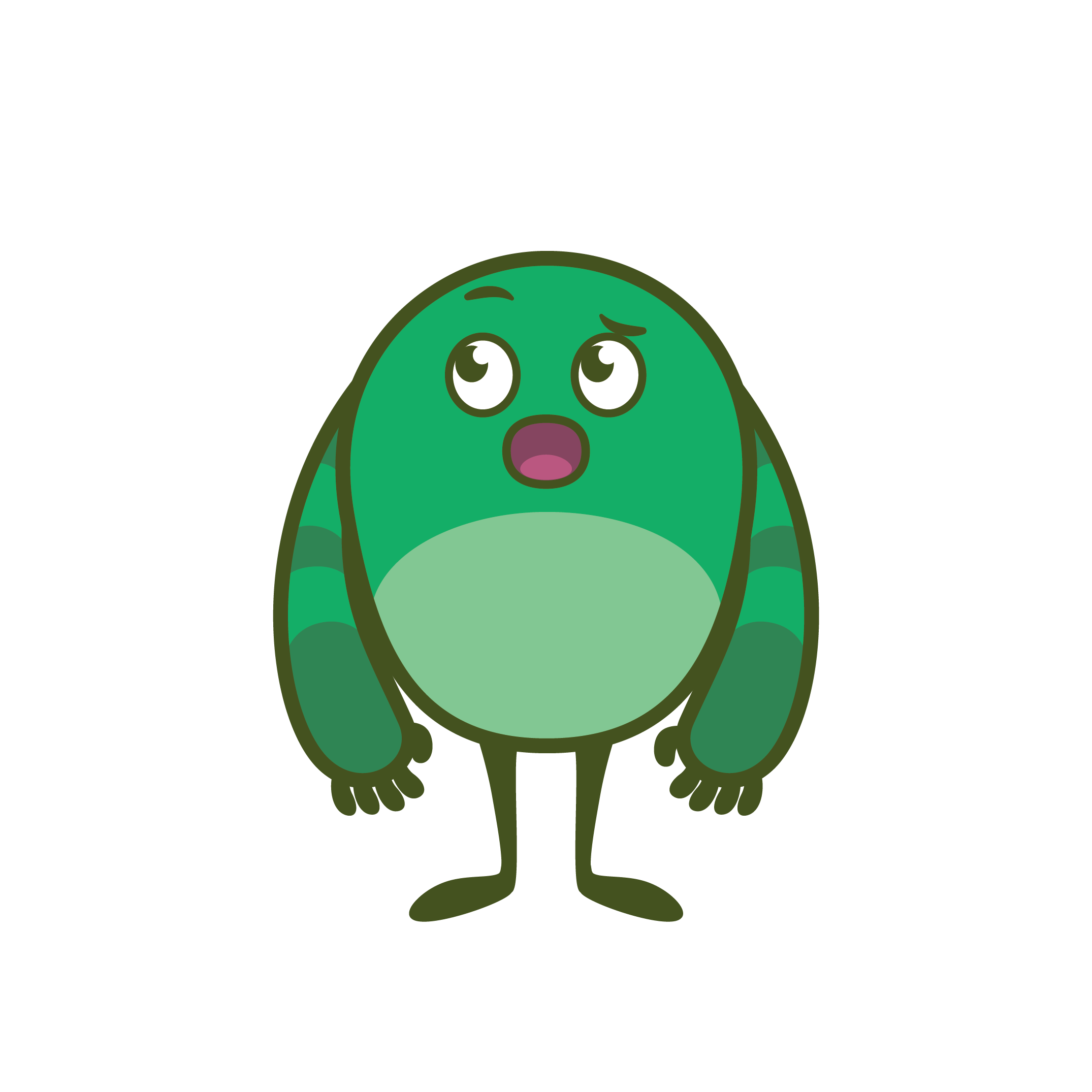
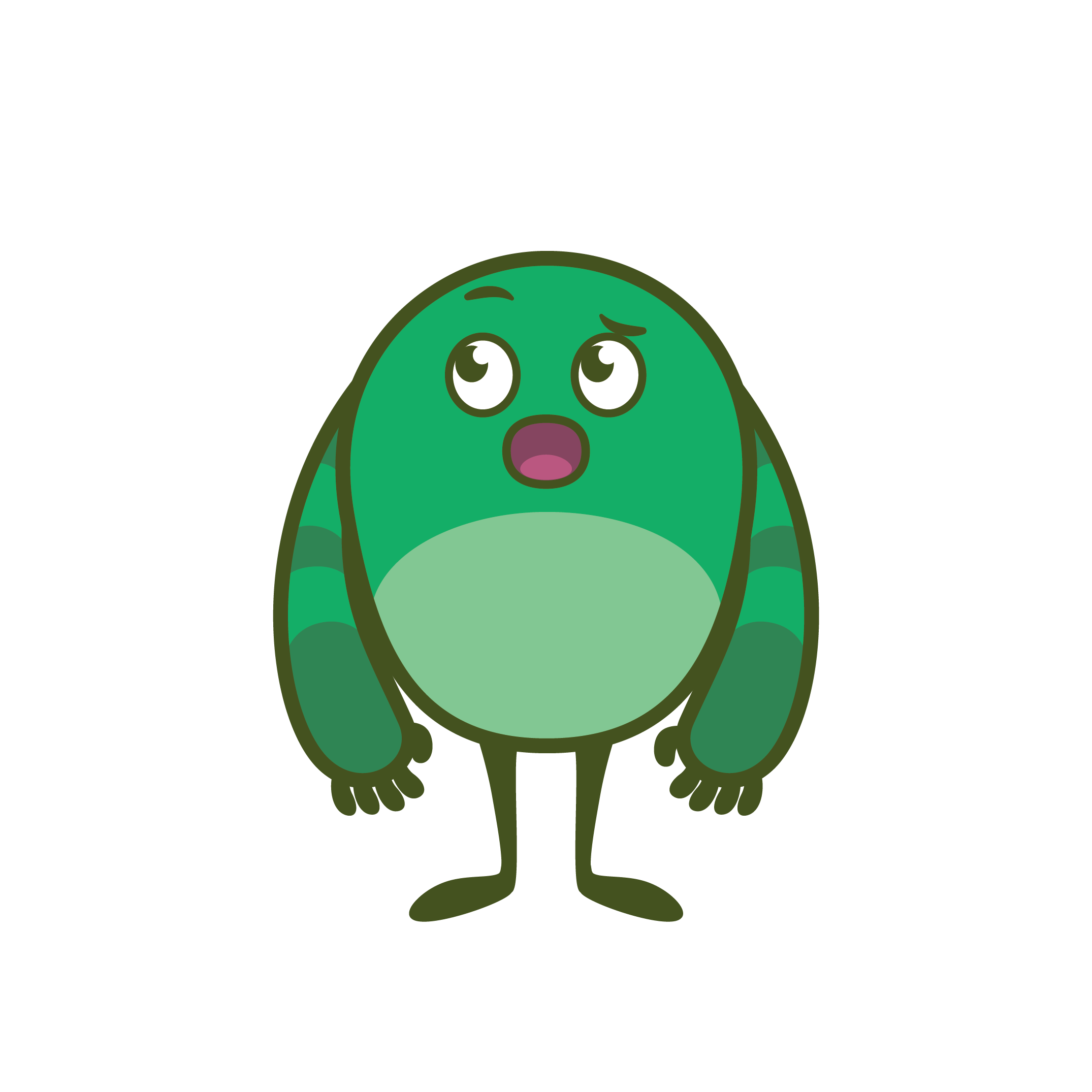
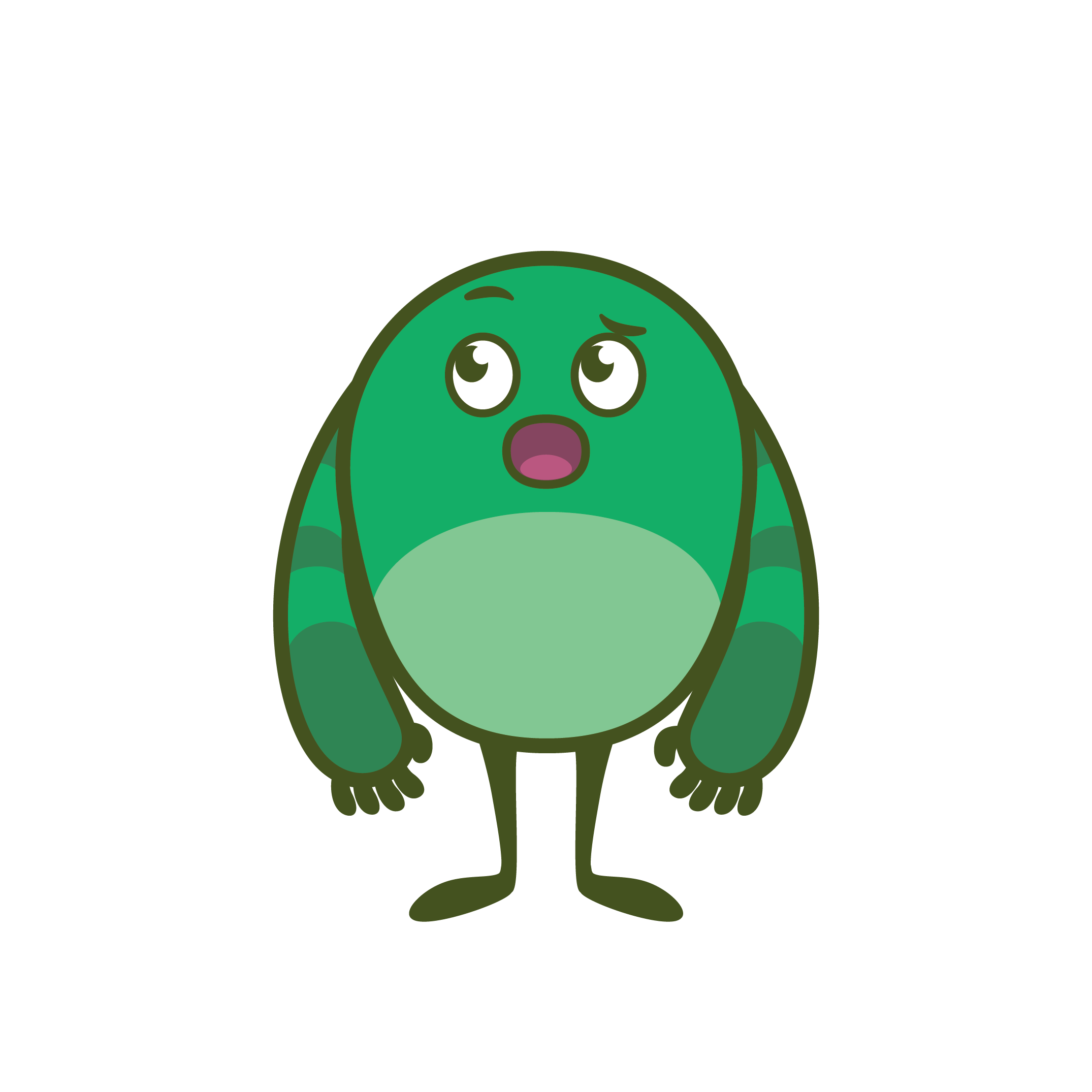
「この漢字はなんと読むんや、ルビさえあれば…」



「めっちゃ便利やん、ルビがなくても難しい漢字が読める!」
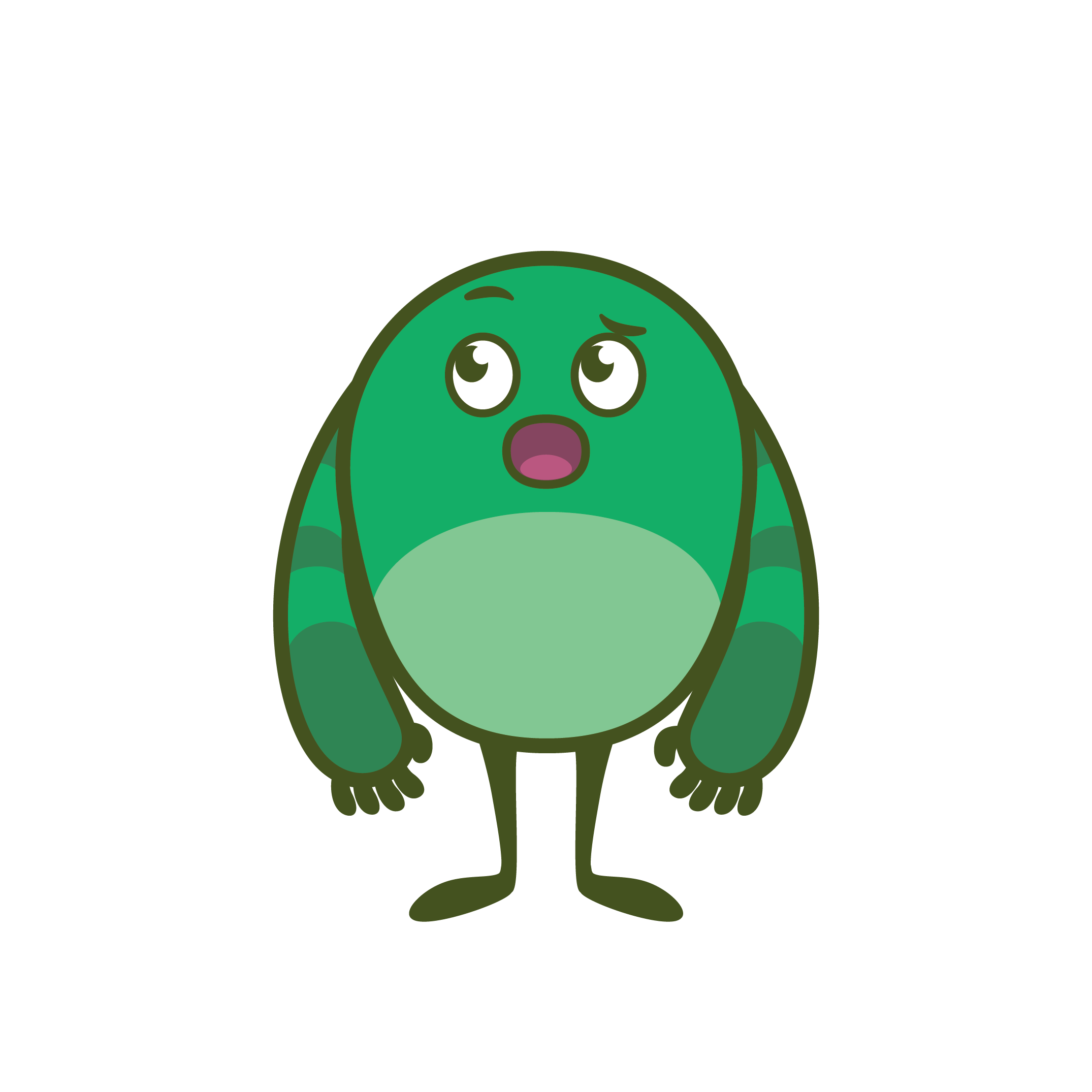
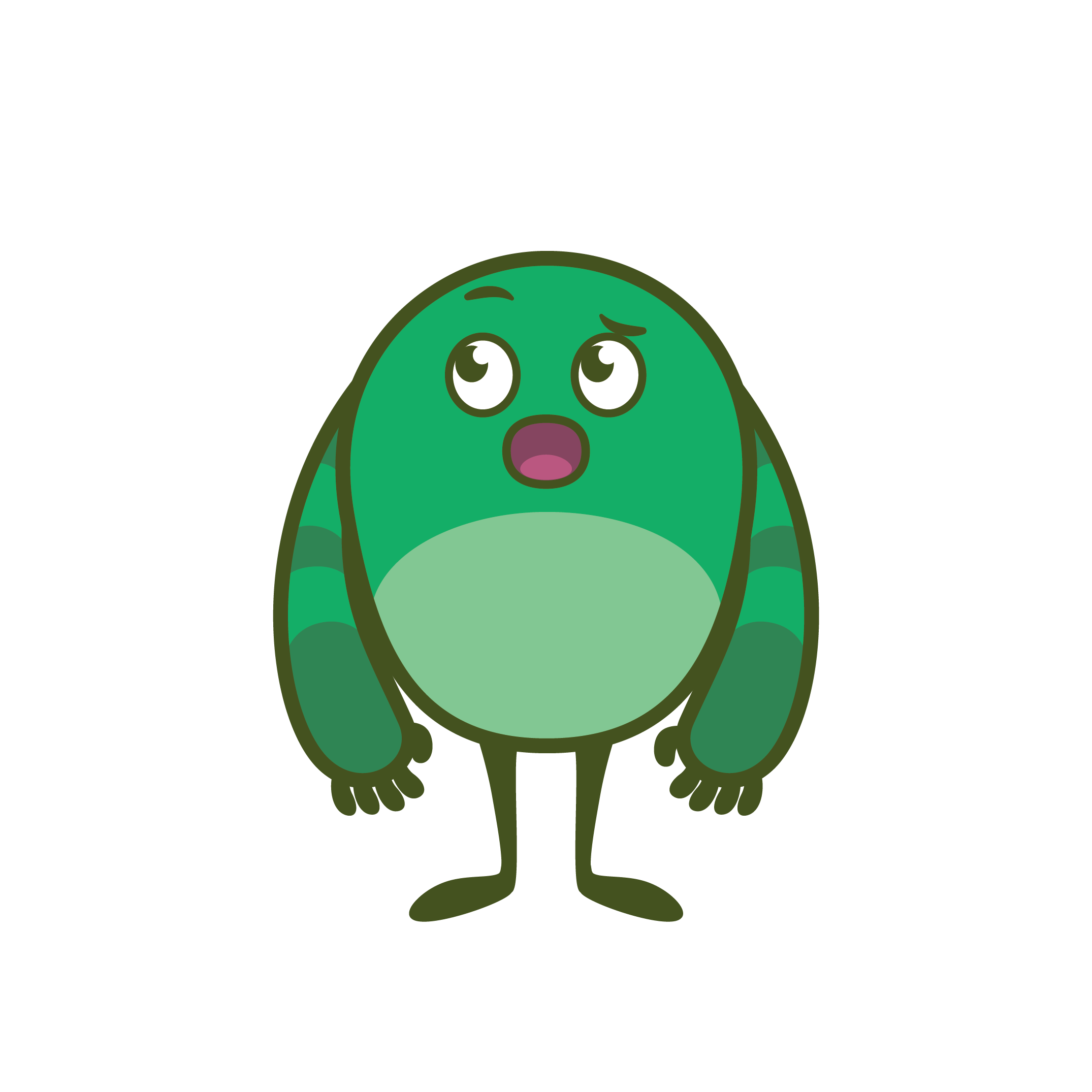
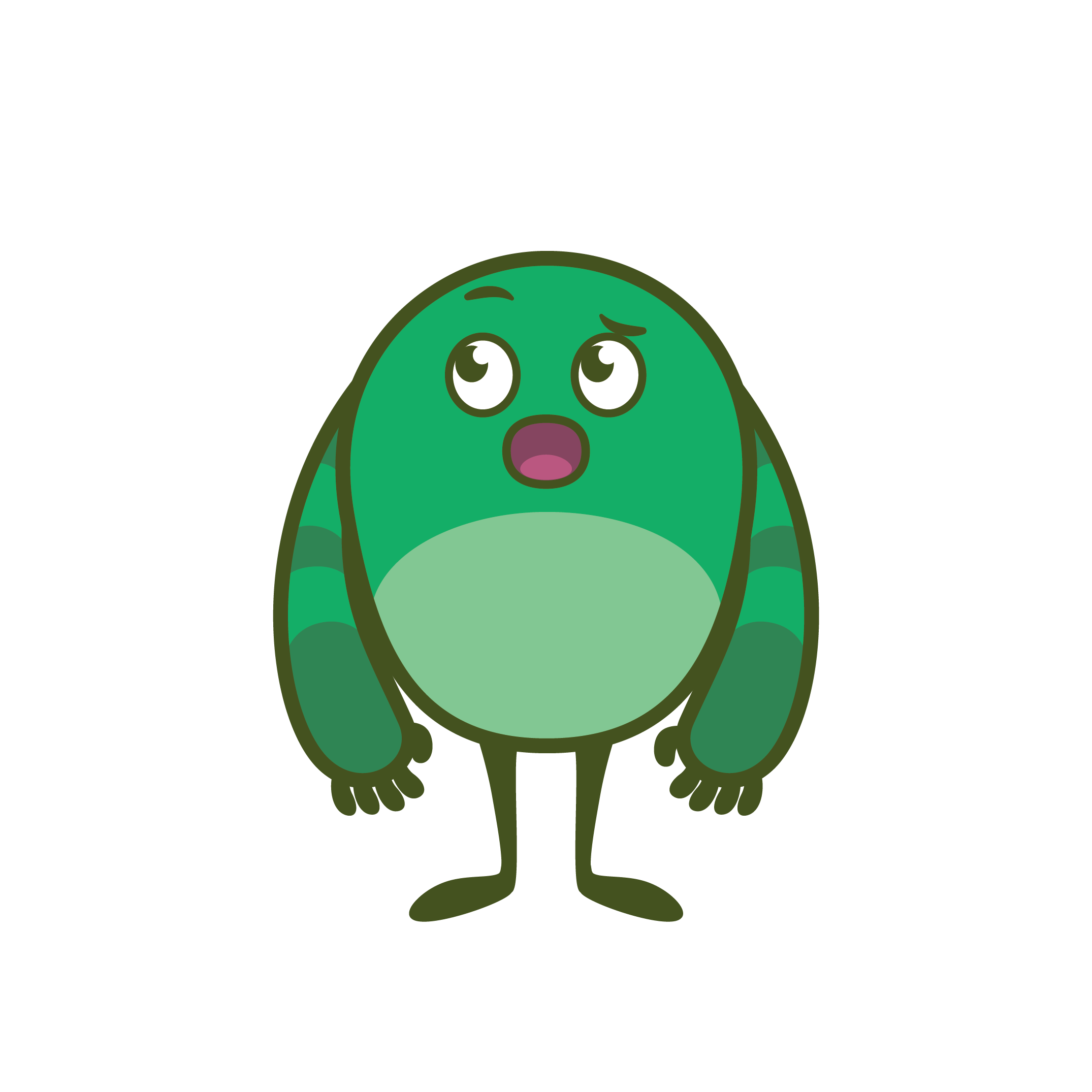
「あれ、見ただけで漢字が読めたぞ。ぼくって成長してる?」
あくまで、理想ですけどね。でも、これが自立を踏まえた支援の構造化です。入口から出口を考えることがポイントです。
漢字にルビがあれば分かるんだけどなー…の状況から、Googleレンズで漢字が読めるようになる体験を想像してみてください。いきなりGoogleレンズの使い方を教えるよりも、支援の効果が高まる可能性大です。
これを書きながら、2024年のMー1のバッテリィズを思い出しました。
「…自転と公転さえ分かればー!!」


これを受けて、『チ。ー地球の運動についてー』公式が「全巻お送りいたします」とのこと
…支援として最高ですよ、これ。
それでは、2025年もよろしくお願いします。みなさんにとって良い一年になりますように。