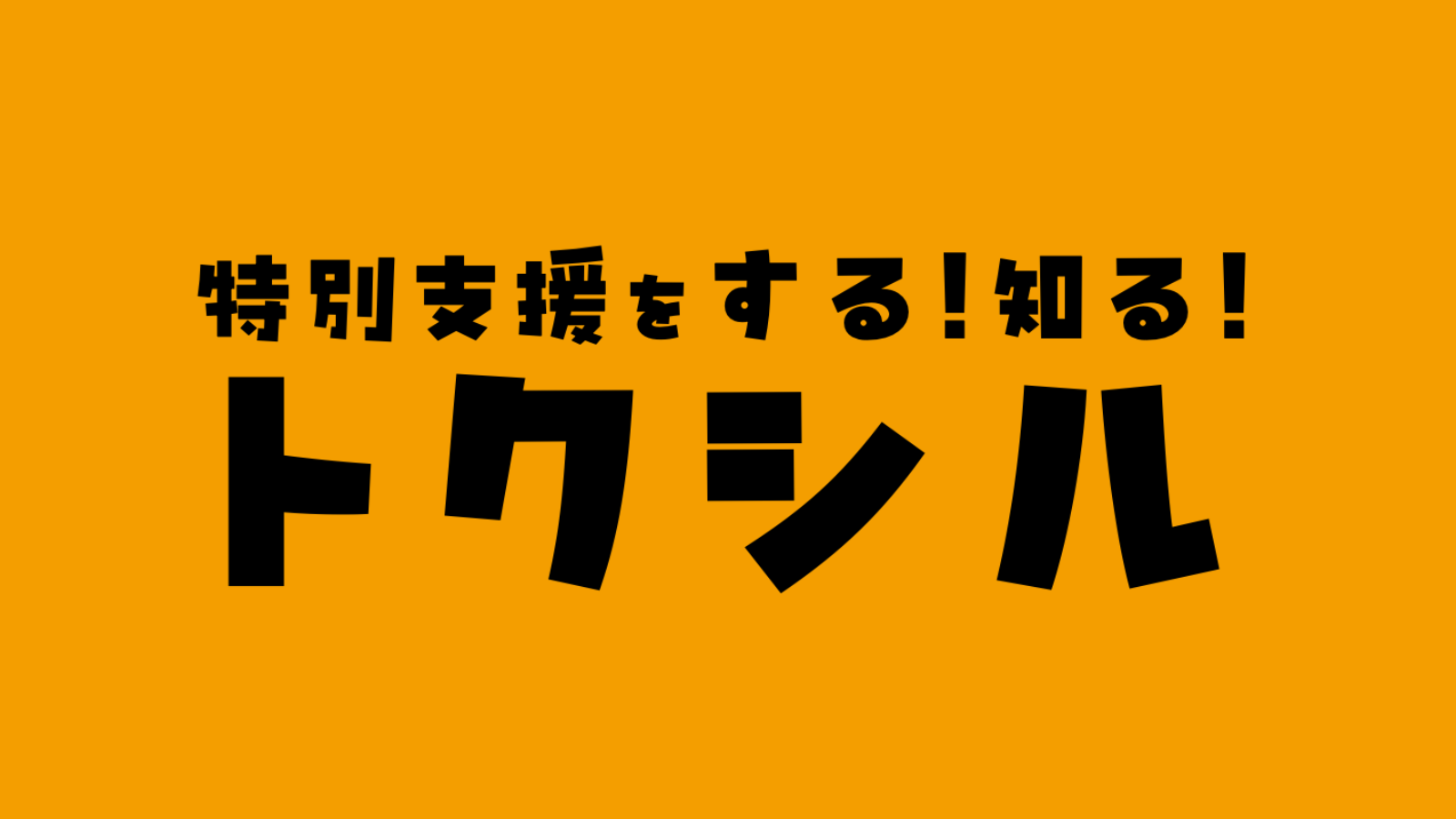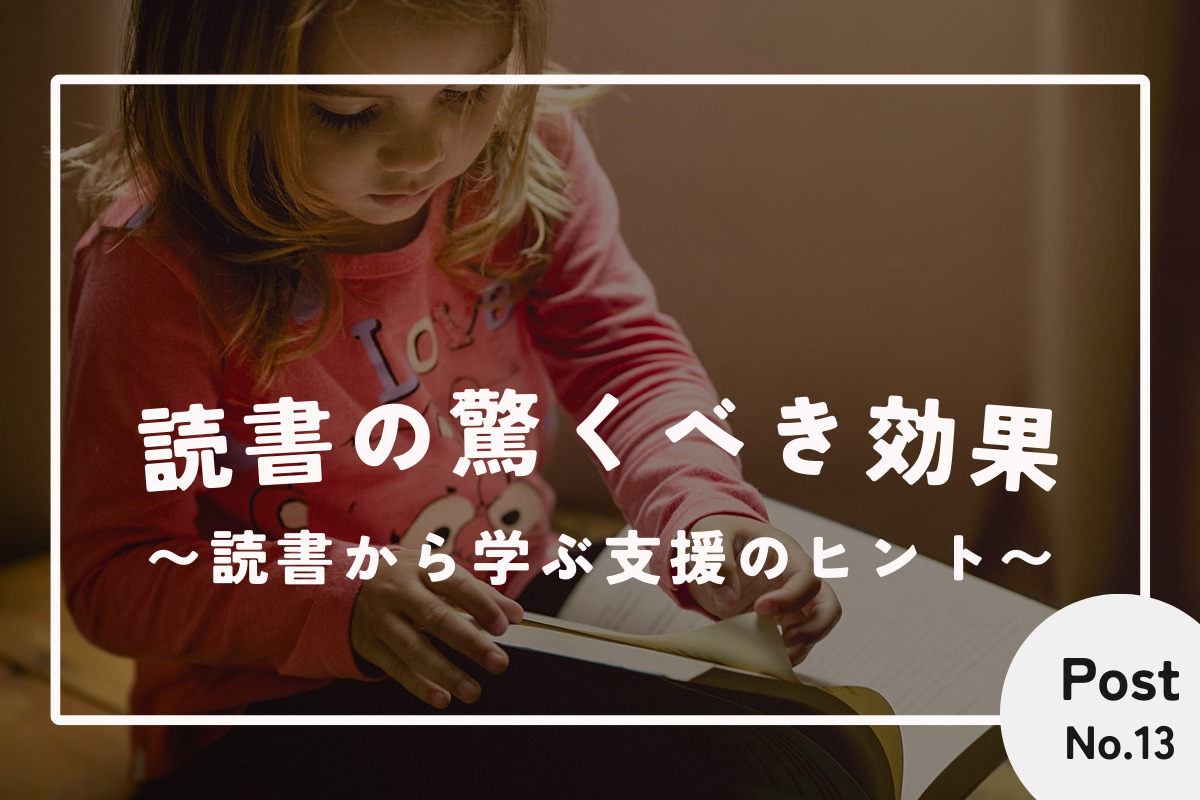読書の驚くべき効果
〜読書から学ぶ支援のヒント〜
 トクシル
トクシルこんにちは!トクシル(@tokushiru)だよー
(悩みを書く)
- 読書には、学習能力の向上やメンタルヘルスの改善など多くのメリットがあること
- 読書には支援のヒントが多く隠れていること
- 子どもの興味関心には共通点や法則があり、次の支援につながる可能性があること
当記事のエビデンス
Neural reactivation in parietal cortex enhances memory for episodically linked information(頭頂皮質における神経再活性化が、エピソード的に結びついた情報の記憶を増強する)
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1800006115
支援のための読書
読書の秋にぴったりな涼しさになってきました。読書に集中できる環境(気温)が整ったと感じます。
最近、興味深いニュースを見つけました。


この記事では、読書が子どもたちに与える素晴らしい効果について述べられています。驚くべきことに、読書は以下のようなメリットをもたらすことがわかっています
- 学習能力の向上(親の教育水準に関係なく)
- メンタルヘルスの改善
- 言語学習による記憶力・計画力・自己制御・実行機能・社会的知性の獲得
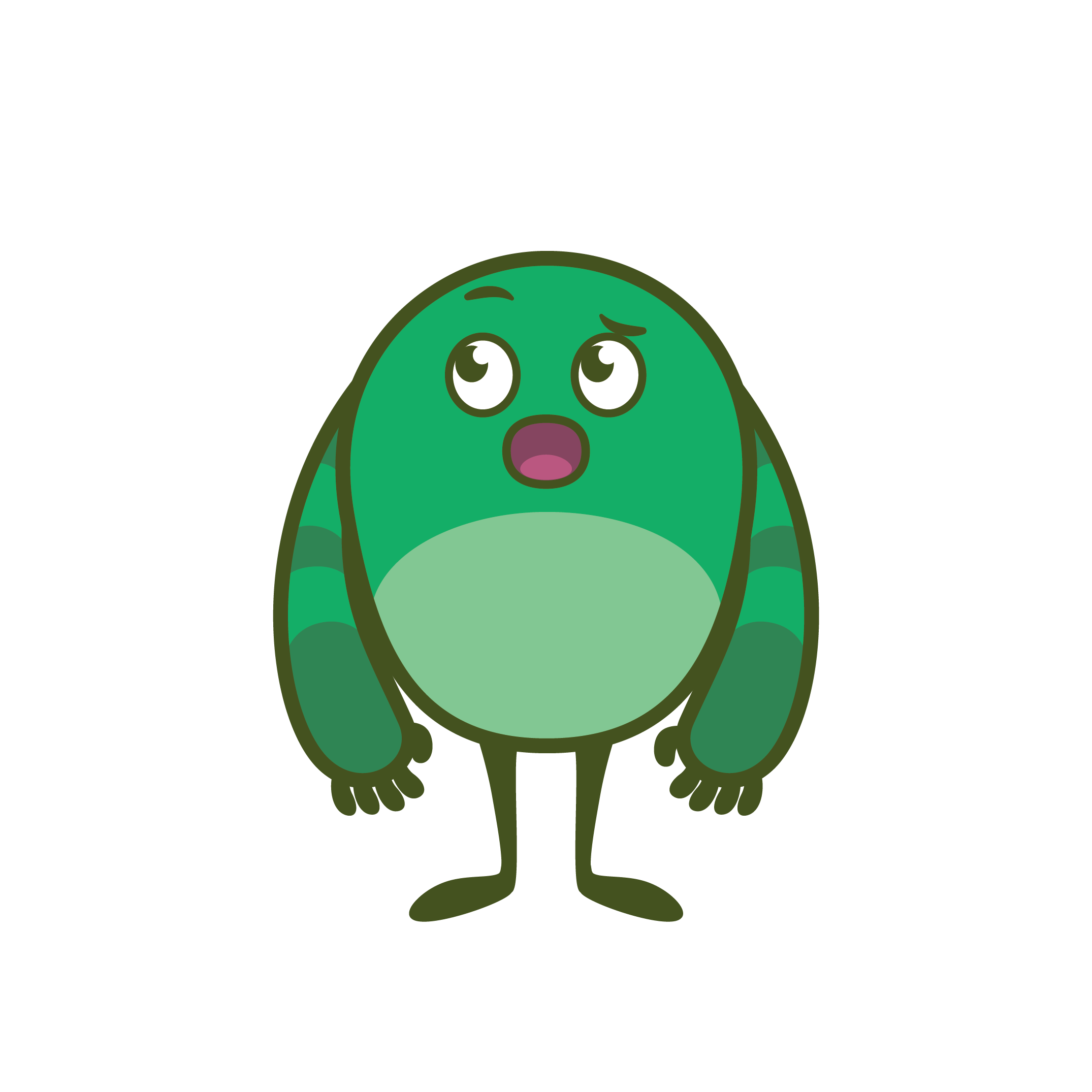
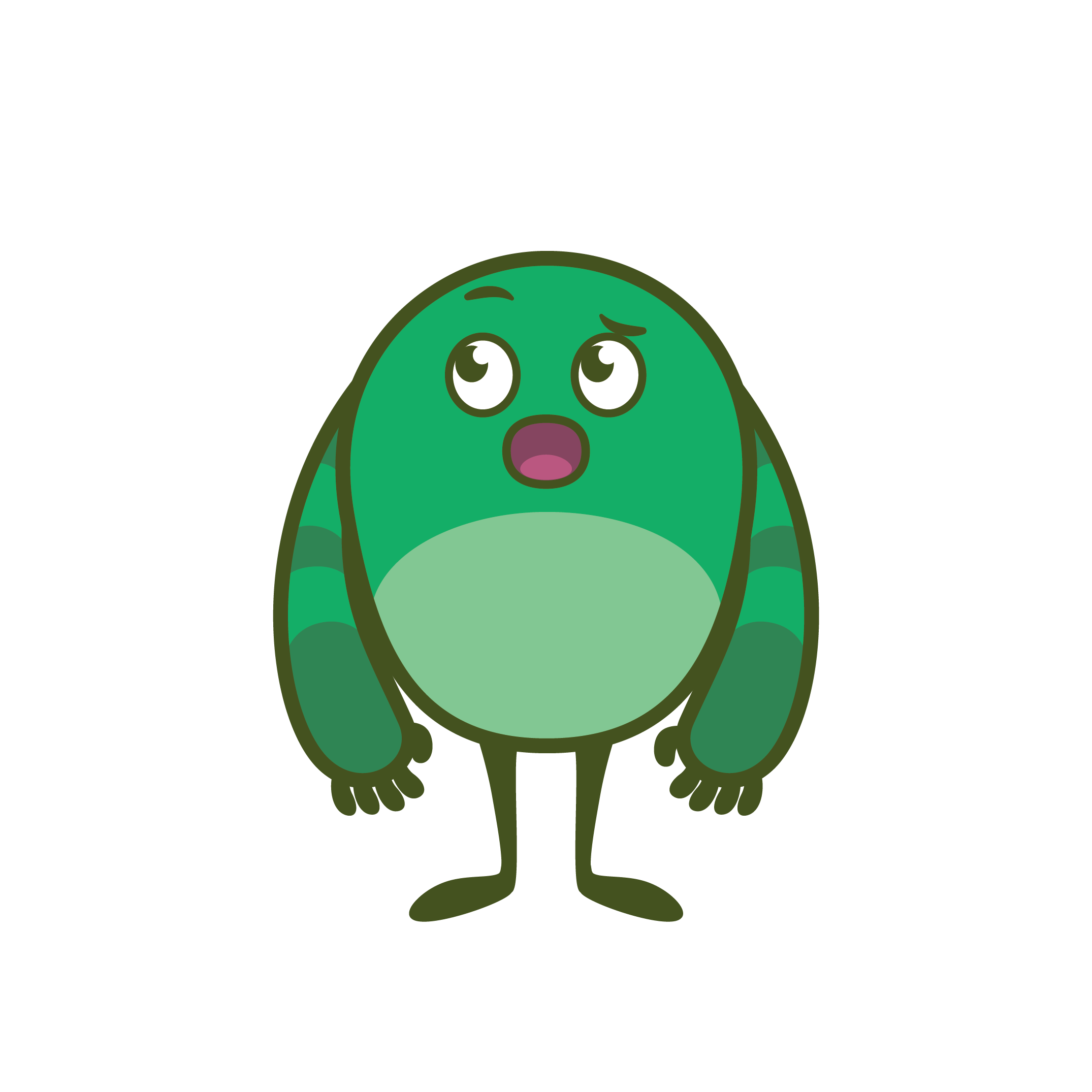
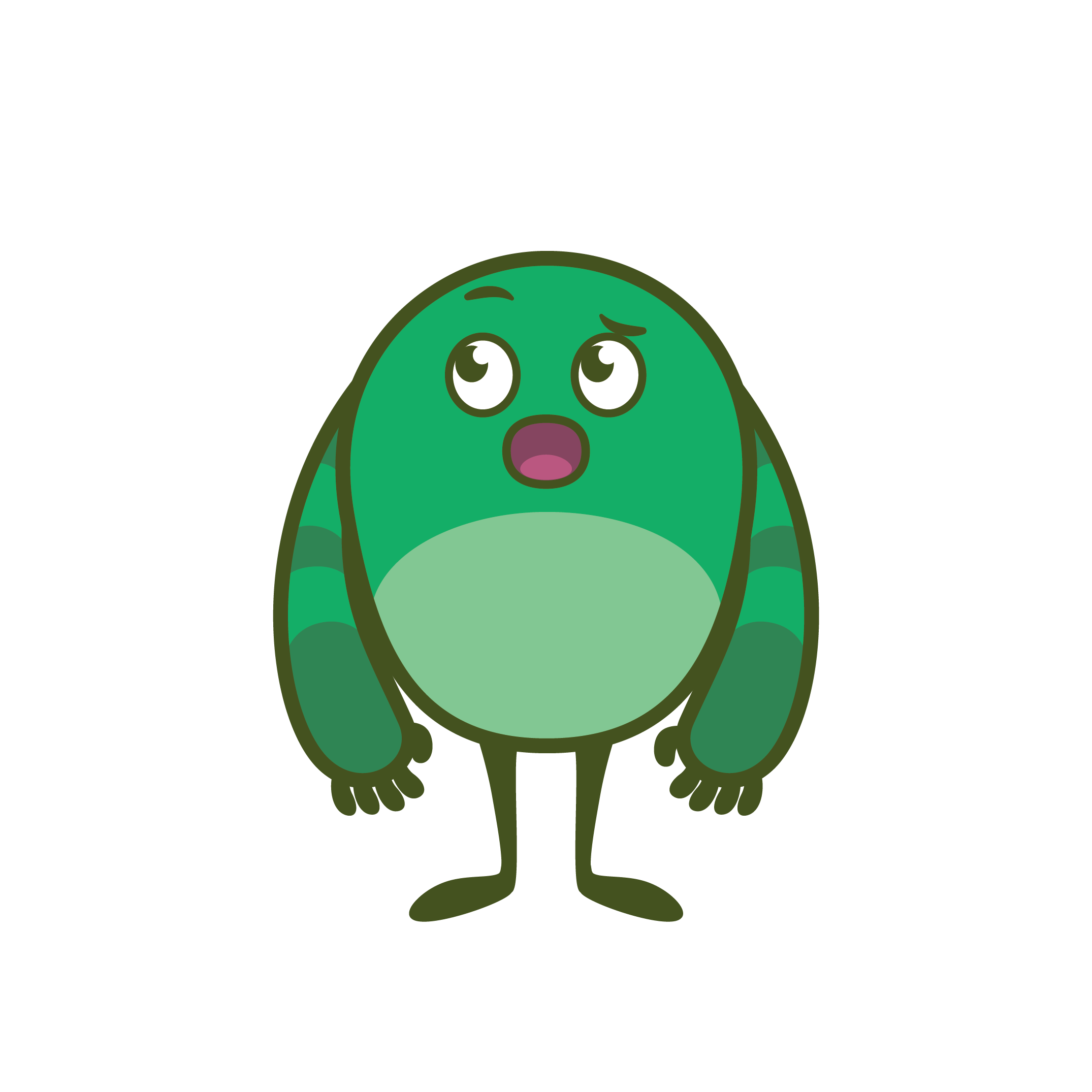
え、読書…すごいな笑
このニュースから、自閉スペクトラム症(以下ASD)を含む知的障害のある子どもたちにとって、読書が有効な支援の一つとなる可能性が考えられます。その理由を詳しく紹介します。
絵やイラストが視覚支援になる
絵本の場合、言葉や文字を理解できなくても、絵やイラストから意味を理解できる可能性があります。
文字と音声のリンクされる
読み聞かせでは、文字と音声が自然とリンクします。例えば「むかしむかし」という文字が理解できなくても、読み聞かせで「mukashi muashi」という音が出されると、子どもは「む」「か」「し」という文字と「mu」「ka」「shi」という音を関連づけることができます。
開始と終了が明白で見通しがもてる
本を開くことで物語が始まり、本を閉じることで終わります。シンプルな構造ですが、これが一人で読書をするハードルを下げ、自立への手助けにもなっています。
共同注意や感情共有のきっかけになる
読み聞かせの場合、自然と共同注意の状態が出来ています。つまり、大人と子どもが同じ本を見ていると、共通の媒体を通じて関わり合うことができます。本の情景や登場人物の感情を共有することは、共同注意では重要です。
記憶の関連づけができる
ストーリーやイラストと関連付けて記憶することは、記憶力を向上させる効果があります。諸説ありますが、スポーツでも同様に、練習では上手くいく技術が本番で再現できないのは、練習環境と技術が関連付けて記憶されていることが原因と指摘する声もあります。
登場人物を俯瞰(ふかん)できる
ASD児は障害特性上、メタ認知が苦手です。悪気もなく相手を怒らせたり泣かせたりしてしまうのは、自分自身を客観的に考えることが苦手だからと考えられています。絵本の場合、人物や動物がコミュニケーションする絵本は登場人物のやりとりを俯瞰(ふかん)してみることができるため、コミュニケーション方法を客観的に理解できる可能性があります。
上記以外にも、まだまだあると思います。
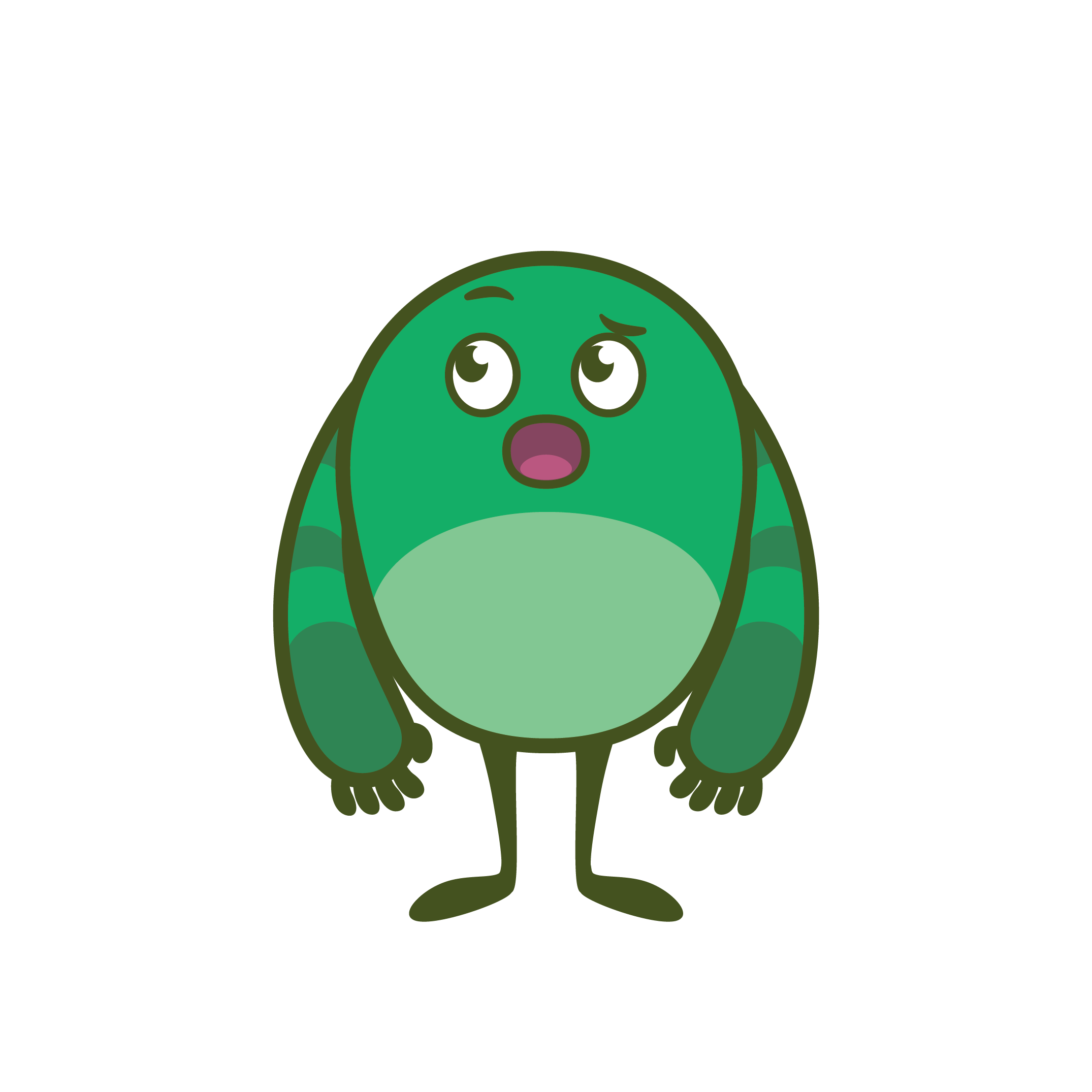
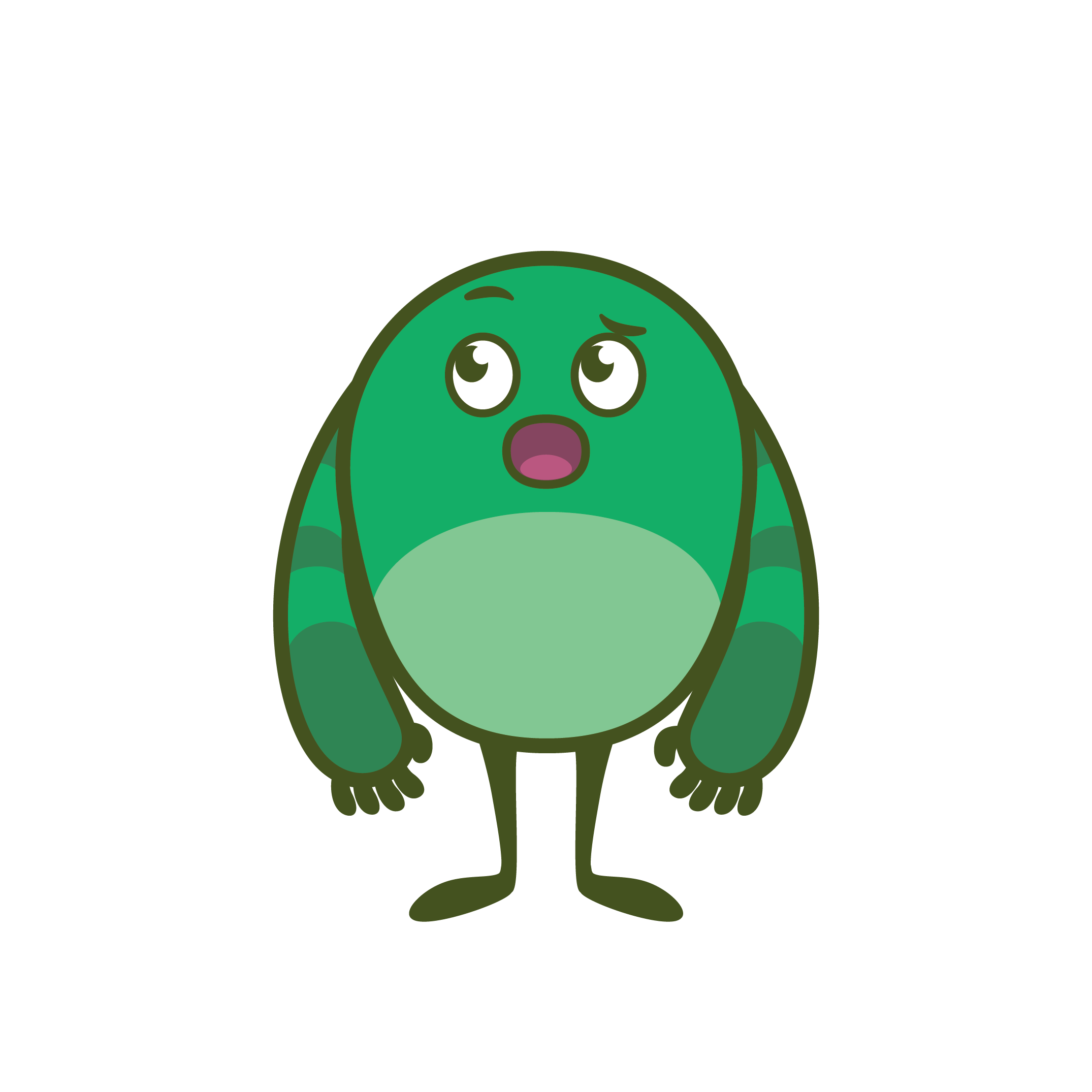
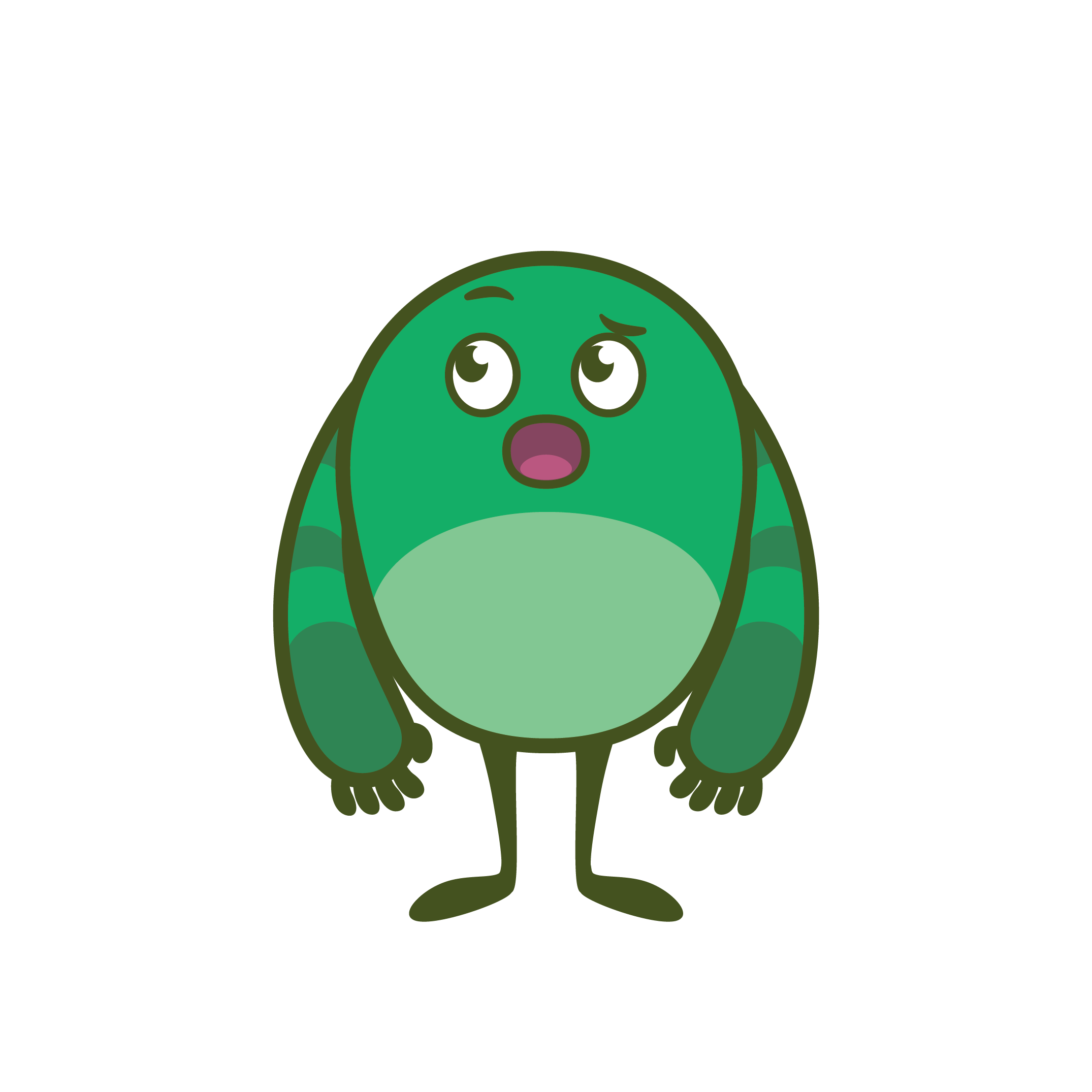
本すげぇ…
本による支援を取り入れようと思っても、絵本の種類は膨大です。選択が難しい場合は、動画サイトの読み聞かせを見て、子どもの目線で絵本を見ることをおすすめします。子どもの目線で本を読むと、本の特徴やメリットがより体感することができます。
エビデンスの解説
タイトルをタップすると
内容を確認できます。
Neural reactivation in parietal cortex enhances memory for episodically linked information
(頭頂皮質における神経再活性化が、エピソード的に結びついた情報の記憶を増強する)
この研究は、記憶の検索プロセスが長期的な記憶の保持を高めることを明らかにしました。具体的な情報や文脈が思い出される過程で、広範なエピソード的文脈が再活性化され、対象と場面の両方の記憶が増強されることが示されました。この再活性化は内側頭頂葉領域と外側頭頂葉領域のネットワークで起こり、記憶の検索が広範な情報の関連性を促進し、海馬と頭頂皮質領域のネットワークがエピソード的な情報の再活性化をサポートすることが示唆されました。
トクシルの考え
本のメリットを他の支援へ生かす
最近ではさまざまな種類の絵本が登場していますが、おすすめや人気という基準だけで選ぶのではなく、支援の観点から選ぶことが大切です。どんなページに対して興味関心をもつのか、いくつか共通点や法則が見えてくるかもしれません。
例えば、
- 特定のページに固執しない
-
ストーリー性を重視している可能性。
- 特定の文字や音声
-
オノマトペ(効果音)や数字、統一したリズム。
- 視線の動き
-
文字やイラストの配置へのこだわり。文字の並び方による読みやすさ(縦書きや横書き等)。
- 現実的か創造的か
-
実生活に近い環境の物語か、現実とはかけ離れた物語か。
など、興味関心の共通点や法則は様々です。全く異なる本同士でも意外な共通点があるかもしれません。
さらに細かい点に注目すると、
- 絵本の材質
-
つるつるかざらざらか、感触のこだわり。
- 文字数やページ数
-
ゆっくり読みたいのか、リズムよく読みたいのか、好みのボリューム。
といった点も支援のヒントになる可能性があります。


こうした共通点や法則を他の支援に活用することで、より本人に適した支援につながる可能性を高めることができます。
たとえば、
- オノマトペに興味関心がある場合
-
子どもとコミュニケーションをする際にオノマトペを使ってみる。
- リズムよく読みたい場合
-
学習の際にリズムを使用して支援する。
などができます。



たかが読書かもしれませんが、支援のヒントは意外と身近にあるかもしれません。



メルカリで絵本を物色しようかなー
- 読書には、学習能力の向上やメンタルヘルスの改善など多くのメリットがあること
- 読書には支援のヒントが多く隠れていること
- 子どもの興味関心には共通点や法則があり、次の支援につながる可能性があること