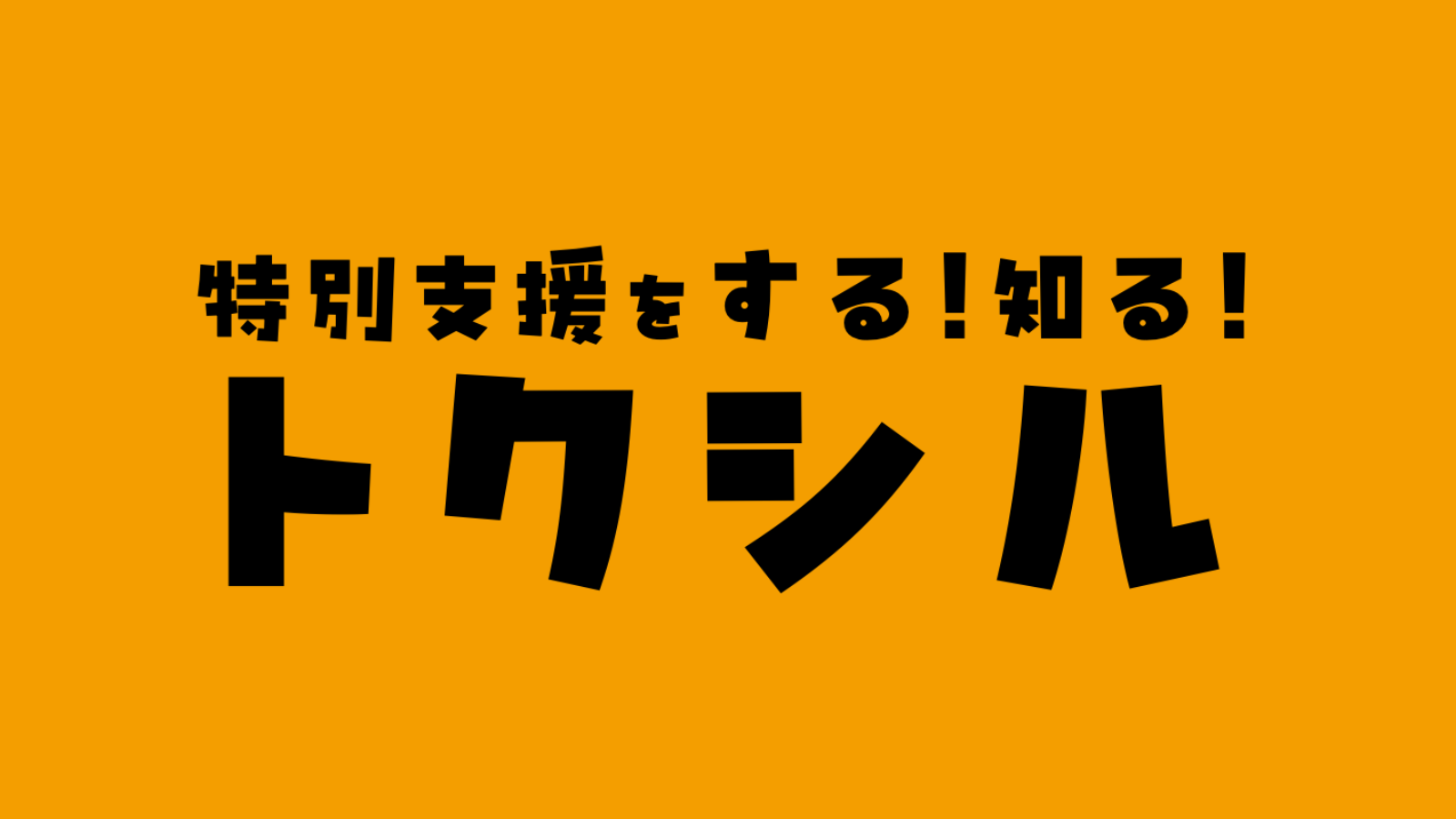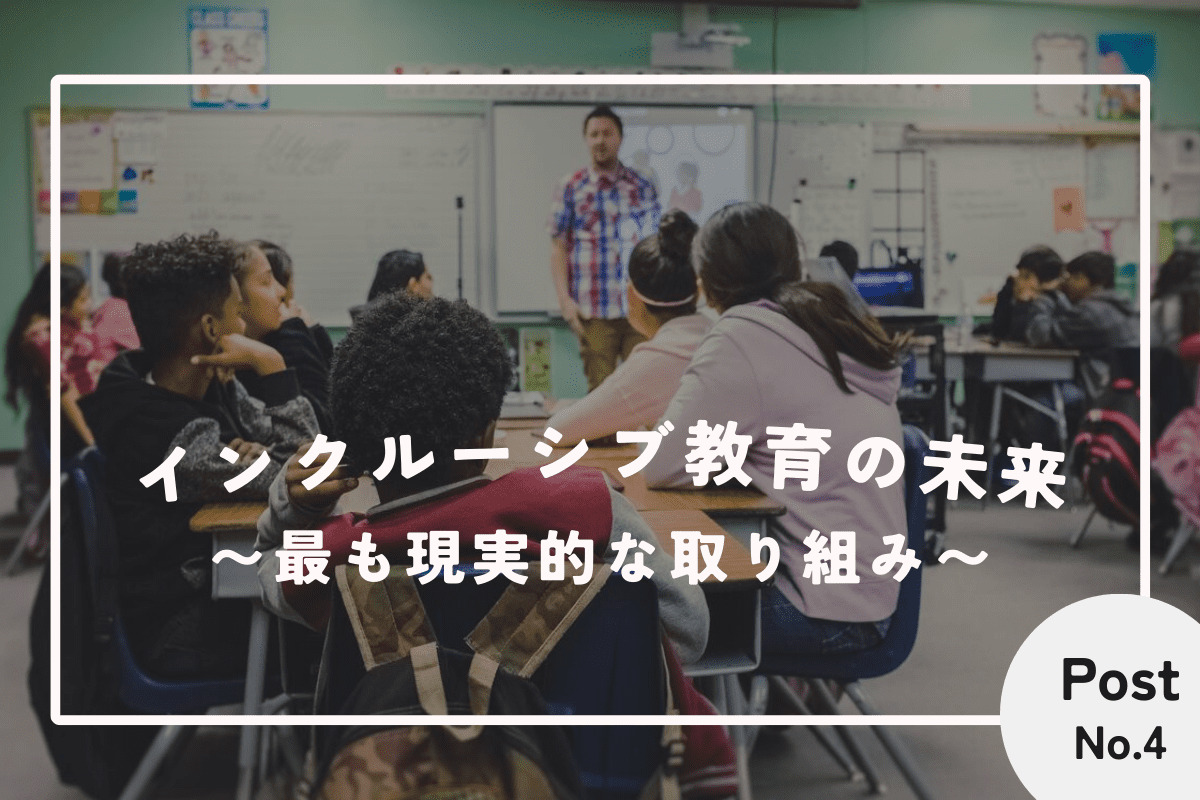インクルーシブ教育の未来
〜最も現実的な取り組み〜
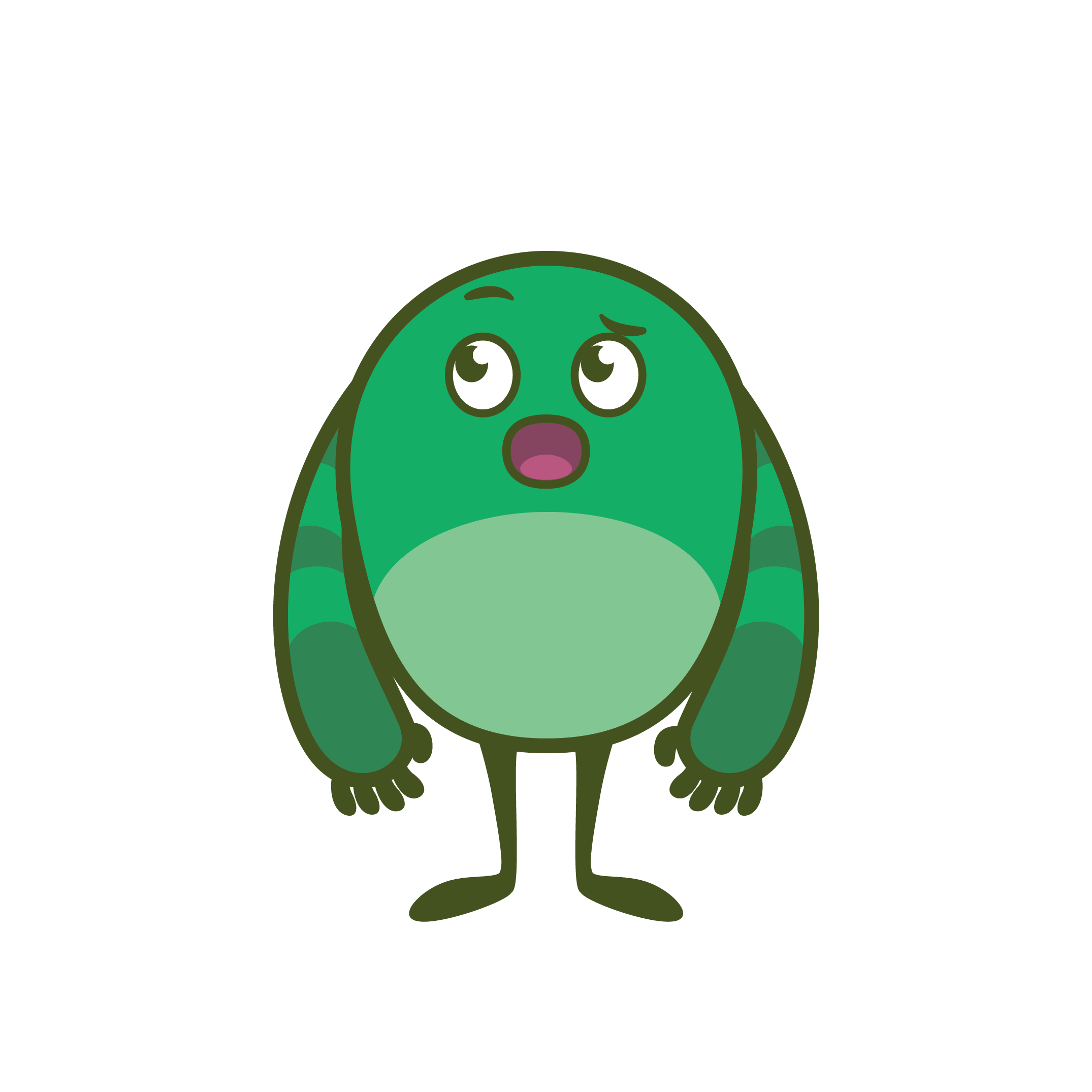 トクシル
トクシルこんにちは!トクシル(@tokushiru)だよー
インクルーシブ教育ってよく聞くけど、結局この先どうなるの?
- 補聴器・人工内耳の進歩によって、聴覚障害がある人でも通常の学校での学習がより現実的になった。
- 国連と日本のインクルーシブ教育に対するアプローチに違いがあること。
- インクルーシブ教育を実現するための環境整備が優先であること。
- インクルーシブ教育は誰のためのものかを考える必要性。
当記事のエビデンス
鳥越隆士.(2012).聴覚障害児のインクルーシブ教育の展開展開(2).イタリア及び米国の公立小学校でのco-enrollmentプログラムの事例から.兵庫教育大学研究紀要.第41巻.2012年9月.pp15-25
https://hyogo-u.repo.nii.ac.jp/records/2162
国連と日本の考え方の違い
インクルーシブ教育とは
要約してくださっている方の文章が分かりやすかったため、一部引用させていただきます。(引用②)(引用③保護されていないため注意)
インクルーシブ教育の目的
- 人間の潜在能力、尊厳、自己の価値の意識を十分に発達させること。人権、基本的自由、多様性の尊重を強化すること。
- 人格、才能、創造力、精神的・身体的な能力を可能な最大限まで発達させること。
- 障害者(国際的には人種・民族・貧富等のマイノリティもおそらく含む)が社会に効果的に参加できること。
実現にむけた「やることリスト」
- 障害を理由に一般的な教育制度、小・中学校から排除しないこと。
- 障害者が他の人と平等であることをベースに、生活地域で受け入れ、質の高い無償の小・中学校教育を受けられること。
- 一人一人に必要な合理的配慮が提供できること。
- 障害者が適切で必要な支援を一般的な教育制度で受けられること。
- 学習と社会的な発達を最大にできる環境で、完全なインクルーシブを目指し、効果的で個別化された支援が提供されること。
要約すると、こんな感じです。
なお、日本は「人格、才能、創造力、精神的・身体的な能力を可能な最大限まで発達させること」を最優先としています。国連は「同じ場で教育を提供すること」が最優先事項です。よって、国連としては、日本の特別支援学級・学校のシステムは不要であり、障害の有無に関わらず一般の小・中学校で学習することがインクルーシブ教育の本質であるということです。
補聴器、人工内耳の進化がとまらない
補聴器や人工内耳は言語発達にも良い影響があるため、補聴器や人工内耳の装着率は年々上昇しています。その結果、聴覚障害があっても聾学校よりも通常の学校を進路先として選択する人が増加しています。聾学校の立場としては寂しい限りですが、社会的には前向きな結果だと考えられます。


エビデンスの解説
タイトルをタップすると
内容が確認できます
鳥越隆士.(2012).聴覚障害児のインクルーシブ教育の展開展開(2).イタリア及び米国の公立小学校でのco-enrollmentプログラムの事例から
イタリアとアメリカの公立小学校で実施されている「co-enrollmentプログラム」を紹介しています。
想像しただけでワクワクする学級ですね!
- アメリカの特別クラスでは、主教師・聾教師・手話通訳者の3名が協力し、こちらも手話環境が整備されている。
- 母国語と手話が行き来するバイリンガル環境になっている。
- イタリアでは、特別クラスに在籍する健常児の成績が、通常クラスの健常児の成績より向上した。ただし、具体的なエビデンスはないため注意が必要。
トクシルの考え
聴覚障害者=手話で話すとは限らない
聴覚障害と一言でいっても、聞こえのレベルは人それぞれです。補聴器や人工内耳の装着率が増えると、手話以外のコミュニケーションとして「口話」や「筆談」が求められる可能性が高まります。口話とは、話し手の口の形や表情から言葉を読み取るコミュニケーション方法の一つです。聴覚障害のある方とのコミュニケーション方法の中では、小・中学生でも実践しやすいと考えます。
口話の詳細はこちらが分かりやすかったです。当事者の方が伝えると説得力が違いますね。



なんだかトクシルも出来そうな気がしてきた!
学習環境のICT化も後押しに
モニターやPCを使用した指導の普及によって、「文字起こし」が可能になりました。指導者の発言が聞き取りにくい場面でも、指導者の発言内容がモニターに表示されることやアーカイブで見直せることは、学習のバリアが減りました。まだまだ、発展途上ですけどね。
インクルーシブ教育は誰のため?
日本の場合、主に障害者が対象です。しかし、国連は障害者を含むマイノリティと健常者が対象です。一個人の意見としては、障害は社会全体の問題でもあるため、国連側の考えの方が理にかなっていると考えます。ただし、海外ではインクルーシブ教育の学習環境がオーバーワークになっている報告もあるため、日本でも同様のことが発生するのではないかと考えています。



インクルーシブ教育をするための環境整備をまず先にやろう!…道は遠いぜ。
- 補聴器・人工内耳の進歩によって、聴覚障害がある人でも通常の学校での学習がより現実的になった。
- 国連と日本のインクルーシブ教育に対するアプローチに違いがあること。
- インクルーシブ教育を実現するための環境整備が優先であること。
- インクルーシブ教育は誰のためのものかを考える必要性。