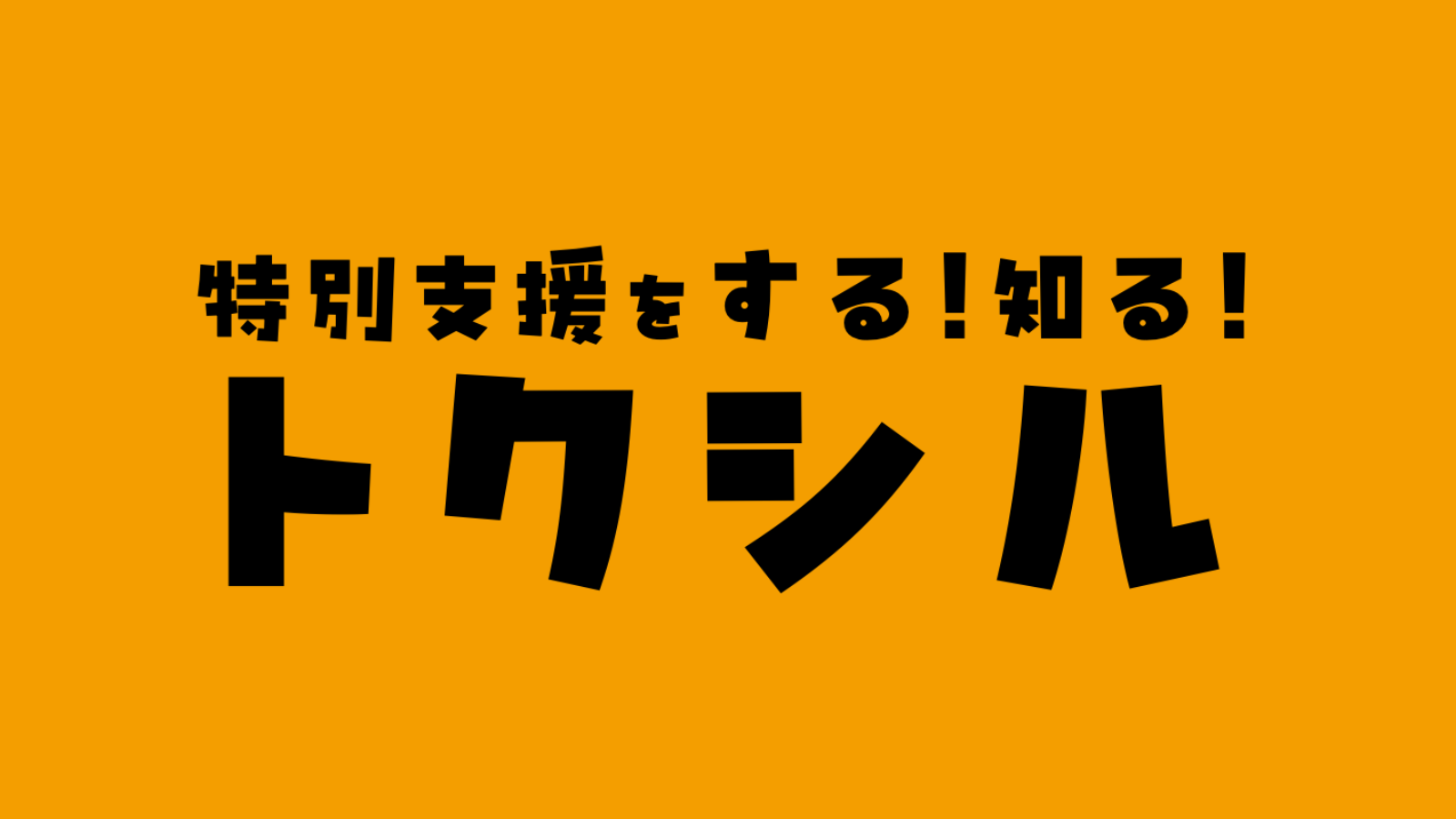アニマルセラピーという支援
〜乗馬療法がもたらす効果〜
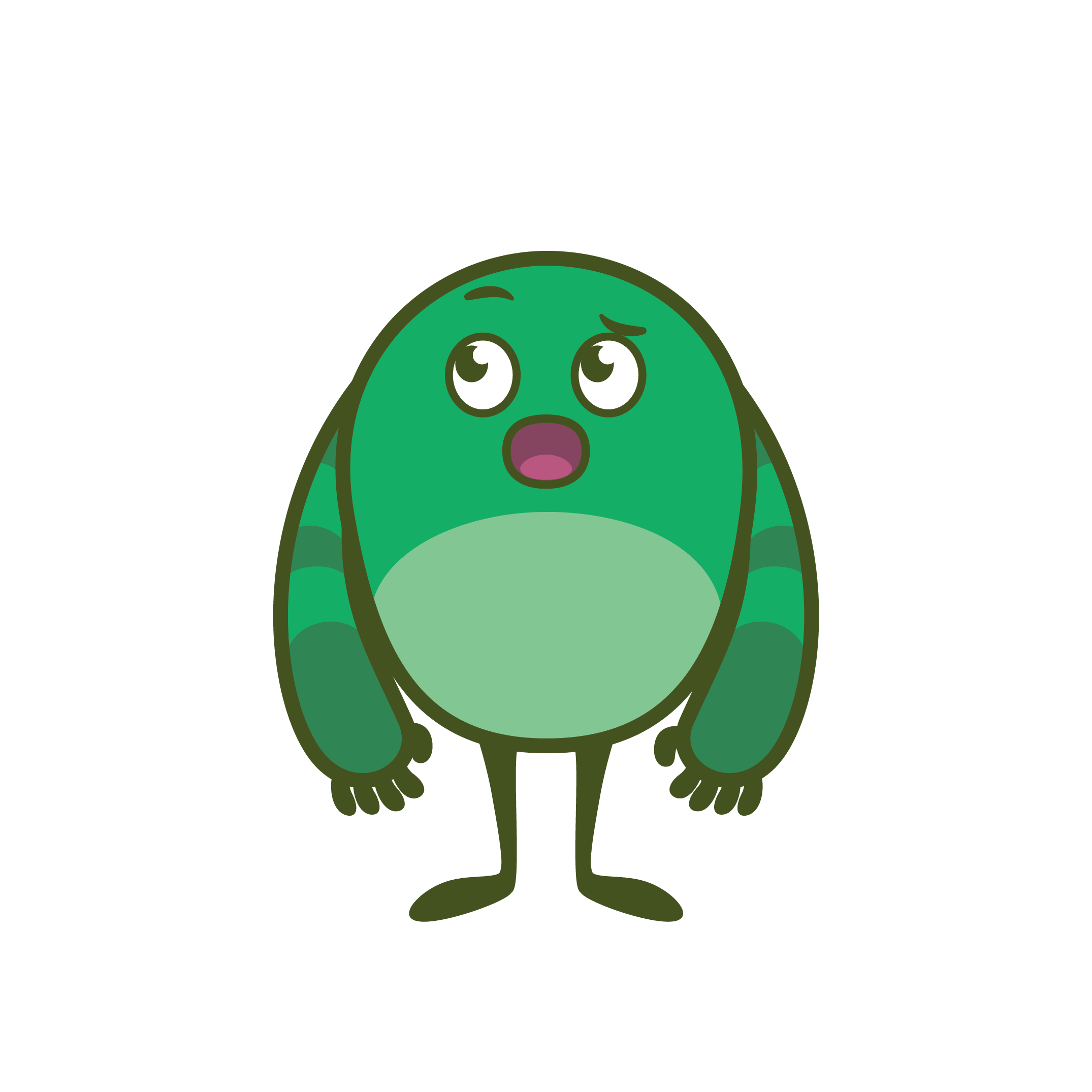 トクシル
トクシルこんにちは!トクシル(@tokushiru)だよー
歩行支援の一つに「乗馬療法」っていうのがあるらしいけど、乗馬が歩行の練習になるの?
- 「アニマルセラピー」という治療・支援の存在
- 乗馬療法は、専門性が高い分野で担い手が少なく、適切な治療法とは言えないものの、障害の改善に関する多くのエビデンスがある。
- 支援において、対象者がゴールを理解していることの必要性
当記事のエビデンス
小川,新野.(2008),身体障害児のための乗馬療法に関する研究,〜乗馬前後の歩行評価からの検討〜.人間工学.第44巻.特別号
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jje1965/44/Supplement/44_Supplement_106/_article/-char/ja/
認知度の低いのはなぜ?
肢体不自由領域の支援の難しさ
肢体不自由者への支援は高度な専門知識と経験が必要であり、他の障害種よりも技術的なスキルが求められることが多いです。支援よりも「介助」というイメージが強いかもしれませんね。
アニマルセラピー、乗馬療法とは
アニマルセラピーとは、動物を介して人々の心身の健康を改善する治療的なアプローチです。その中でも馬を利用した治療として「乗馬療法」があります。乗馬療法の目的は以下の通りです。
- 心のリラックスとストレス軽減
-
動物とのふれあいがリラックス効果やストレス軽減につながり、心身のリフレッシュが期待できる。
- コミュニケーションの向上
-
動物とのふれあいは、コミュニケーションスキルの向上に役立つ可能性がある。特に自閉スペクトラム症の人にとって、アニマルセラピーはコミュニケーションを促進する手段として効果的である。
- 身体的なリハビリテーション
-
動物を利用した運動療法や物理療法が、身体的なリハビリや運動障害の治療に役立つ可能性がある。
- 社会的結束の促進
-
アニマルセラピーは、グループセッションや共同作業を通じて、参加者間の社会的結束を高めるのに役立つ可能性がある。
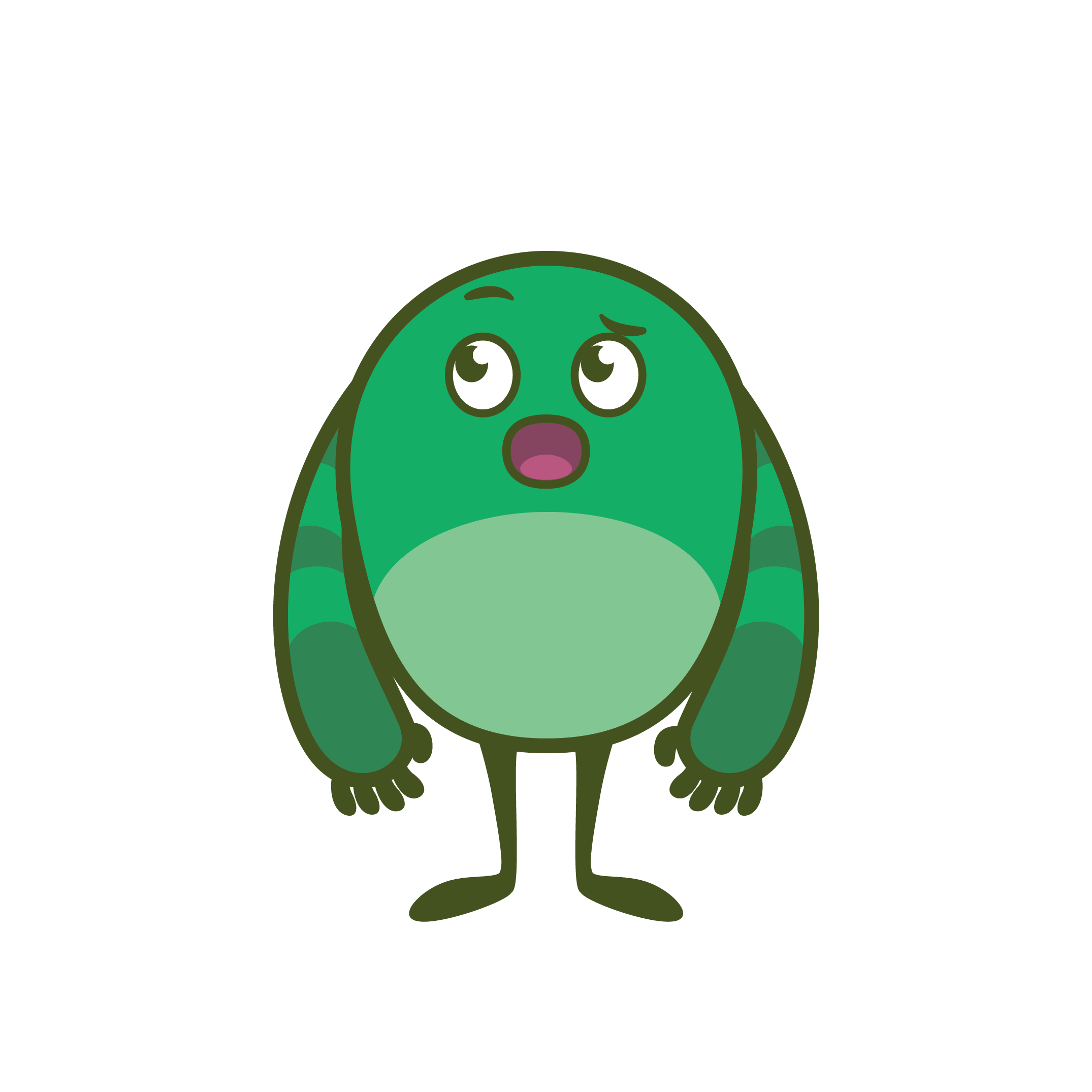
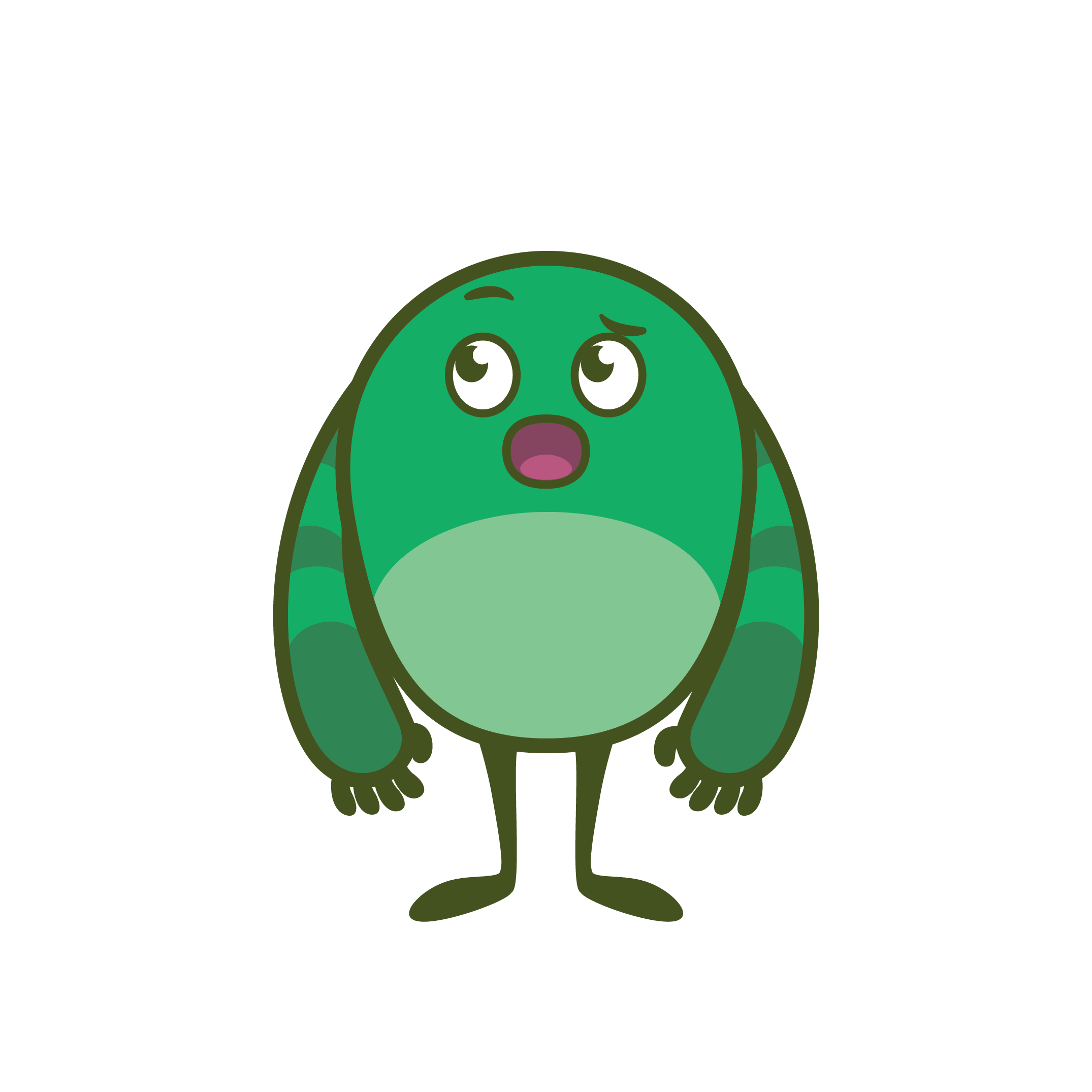
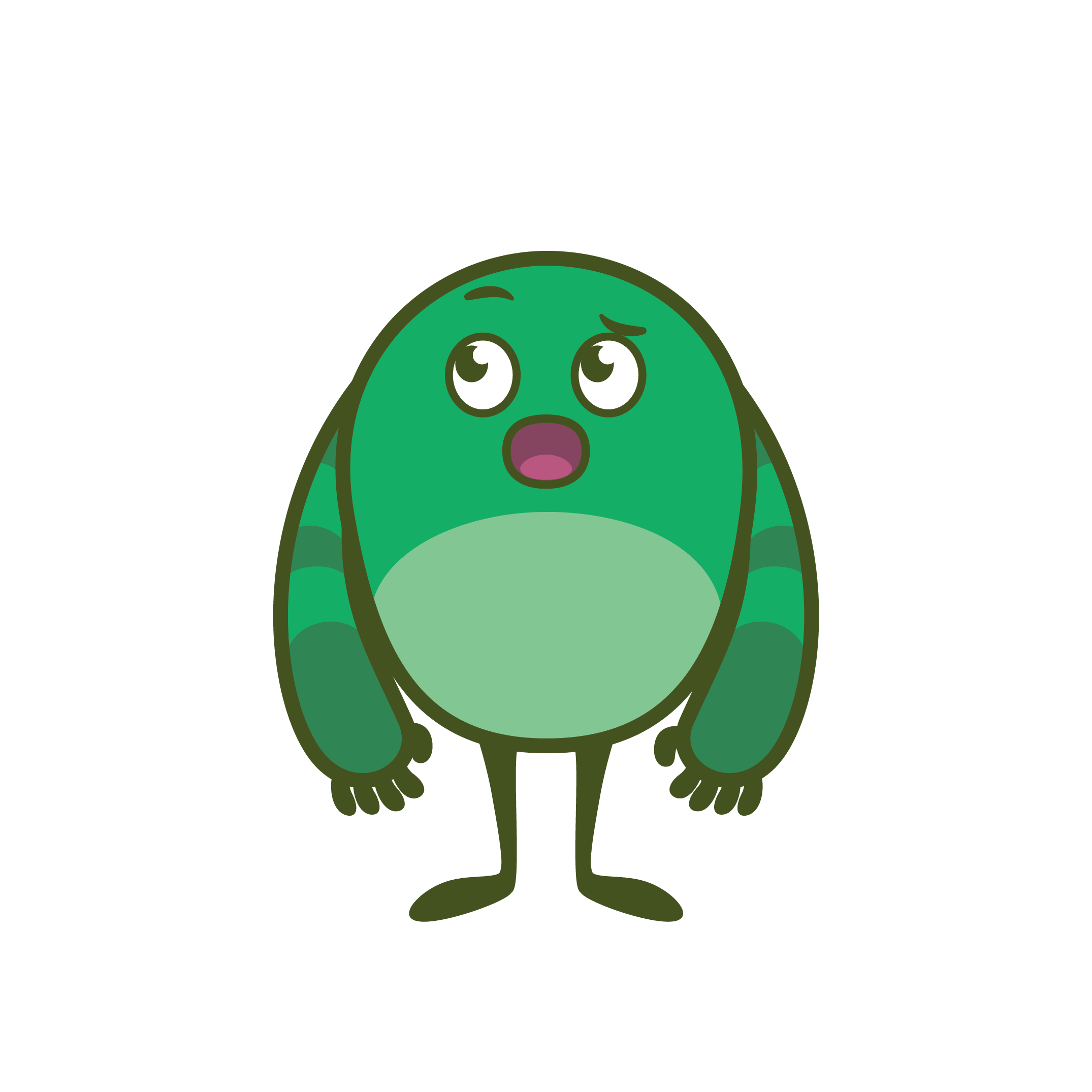
いろんな効果があるんだね。なぜ知らなかったんだろう。
専門性の高さによる担い手の少なさ
アニマルセラピーは多くの専門性が求められる治療法であると考えます。
- 特別支援や障害に関する知識
- 動物の生態に関する知識
- 日常生活の改善を目指した作業療法の知識
これらの要素はいずれも高度な専門知識が求められます。文献や情報が少ないことも担い手の少なさを裏付ける根拠となっていると考えます。また、アニマルセラピーは「治療」という側面が大きいため、文献や情報の対象の多くが、重度の障害者となっていると考えられます。
エビデンスの解説
タイトルをタップすると
内容が確認できます
小川,新野.(2008),身体障害児のための乗馬療法に関する研究,〜乗馬前後の歩行評価からの検討〜
障害児9名(障害種はバラバラ)を対象に、乗馬療法の効果を調査しました。障害種によって効果に差がみられましたが、乗馬前後の歩行スキル(歩行ストライド・歩行速度・歩行テンポ)において一定の改善が認められました。
小川,新野.(2008),身体障害児のための乗馬療法に関する研究,〜乗馬前後の歩行評価からの検討〜
日本とアメリカの乗馬療法を比較し、日本の乗馬療法が浸透していない原因を調査しました。その結果、乗馬療法の資格が取得できる機関が少ないことや有資格者が活躍できる乗馬施設が少ないことが、担い手不足の一因につながっていることを指摘しました。
トクシルの考え
乗馬療法が採用されないのはなぜか
動物による治療は、良くも悪くも治療効果が不安定なのではないかと考えます。
人間による治療ではマニュアルが存在し、安定した治療効果が期待できるものの、動物の場合はそうもいかないですよね。また、動物との相性もあるでしょう。しかし、症状が改善するケースが多々あることも事実であり、支援の選択肢を増やすという考え方もよいかもしれません。
愛知県で実施している事業所
※他にも実施している事業所はあると思います。
治療ではなく、「支援」という見方
肢体不自由の人が乗馬療法をすることによって、
- 新たな視覚的・感覚的な体験ができること
- 通常の生活では経験できないような風景や感触があること
- 動物の予測不能な動きに対応すること
などが経験できると考えます。個人的には、治療や支援を継続した姿(ゴール)をイメージできることが乗馬療法の魅力だと感じました。これは、特別支援でも重要な視点です。今後、支援の選択肢の一つとして普及してほしいです。



ドラ◯ン桜でも、東大受験前に実際に東大行ってたな。
合格をイメージすることが大切って。
- 「アニマルセラピー」という治療・支援の存在
- 乗馬療法は、専門性が高い分野で担い手が少なく、適切な治療法とは言えないものの、障害の改善に関する多くのエビデンスがある。
- 支援において、対象者がゴールを理解していることの必要性