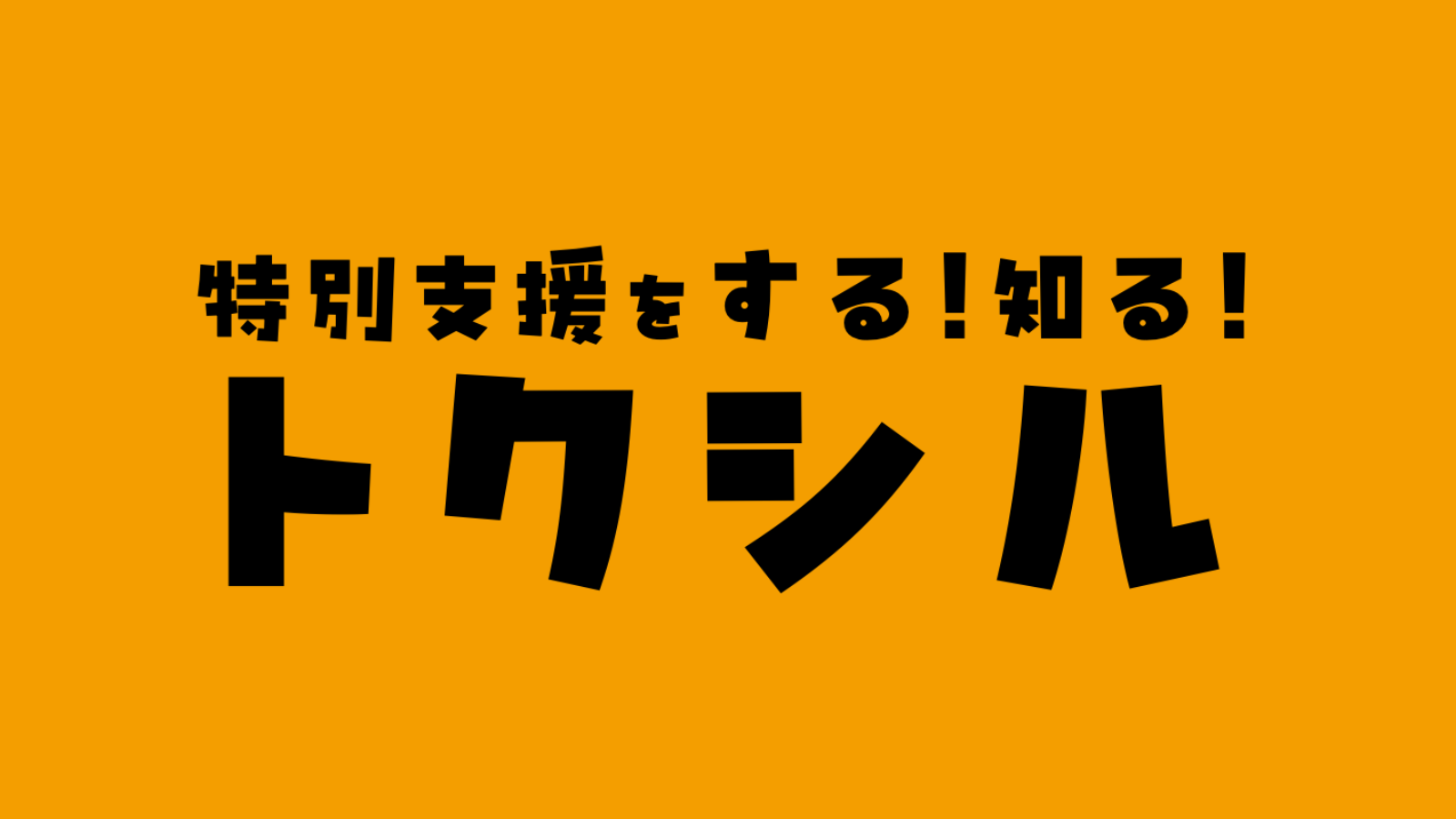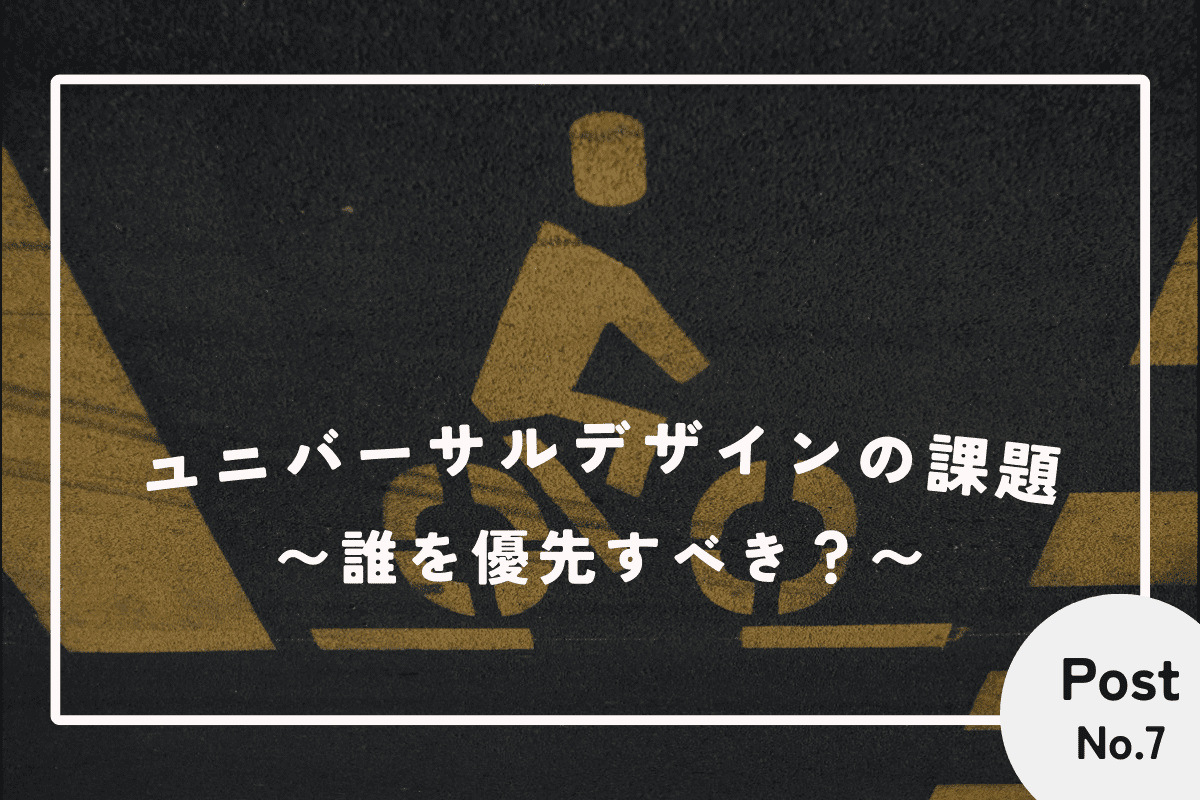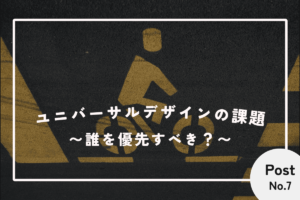ユニバーサルデザインの課題
〜誰を優先すべき?〜
 トクシル
トクシルこんにちは!トクシル(@tokushiru)だよー
みんなにとって使いやすいのって素晴らしいよね!
- ユニバーサルデザイン・バリアフリー・合理的配慮の違い
- 行政の政策において、ユニバーサルデザインよりも耐震化・老朽化への対策の方が優先度が高いこと
- 多様性を複数箇所で実現する個別最適型ユニバーサルデザインの方が利用しやすいこと
当記事のエビデンス
総務省.バリアフリーとユニバーサルデザイン
https://www.soumu.go.jp/main_content/000546194.pdf
なんかややこしい言葉たち
ユニバーサルデザインとバリアフリーは何が違うの?
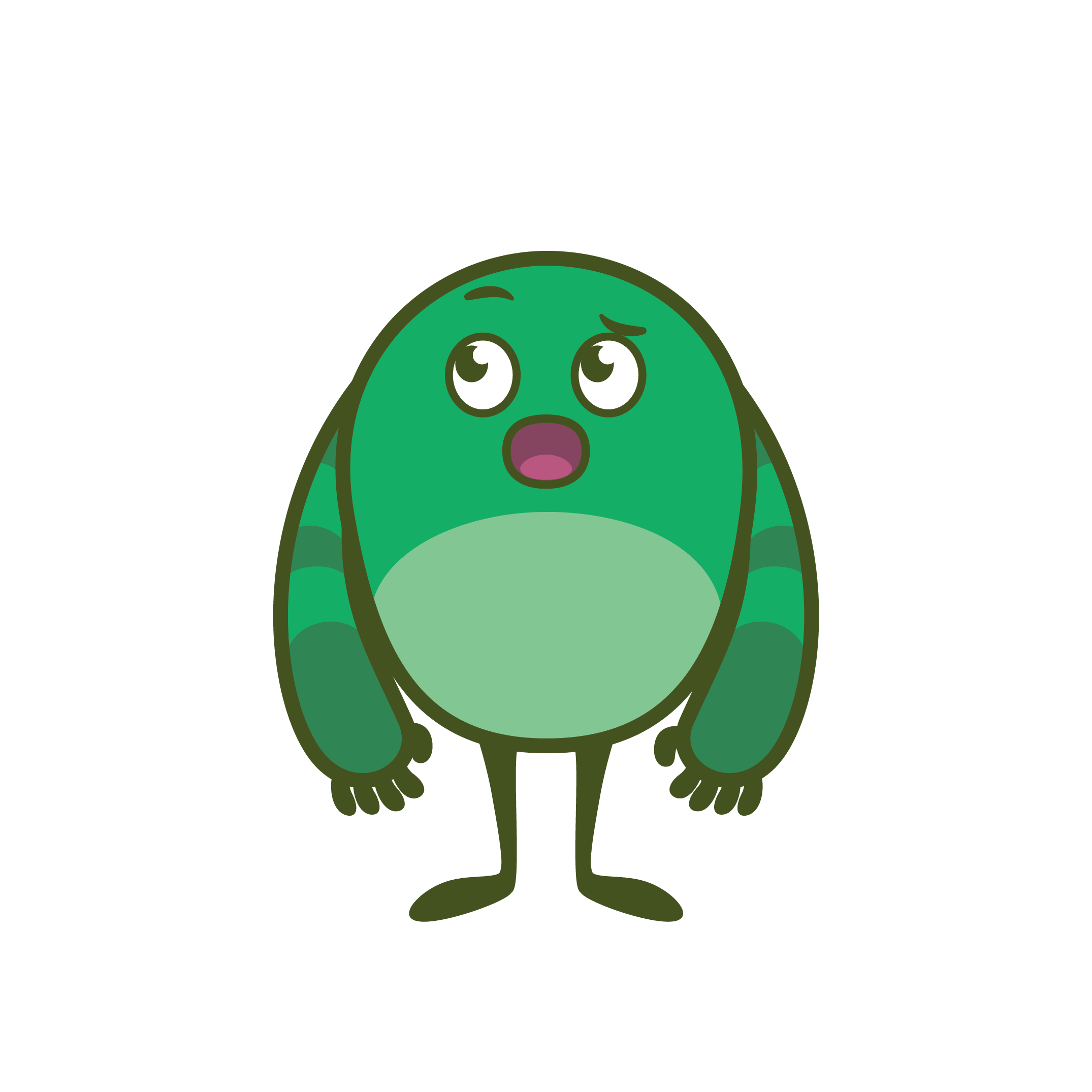
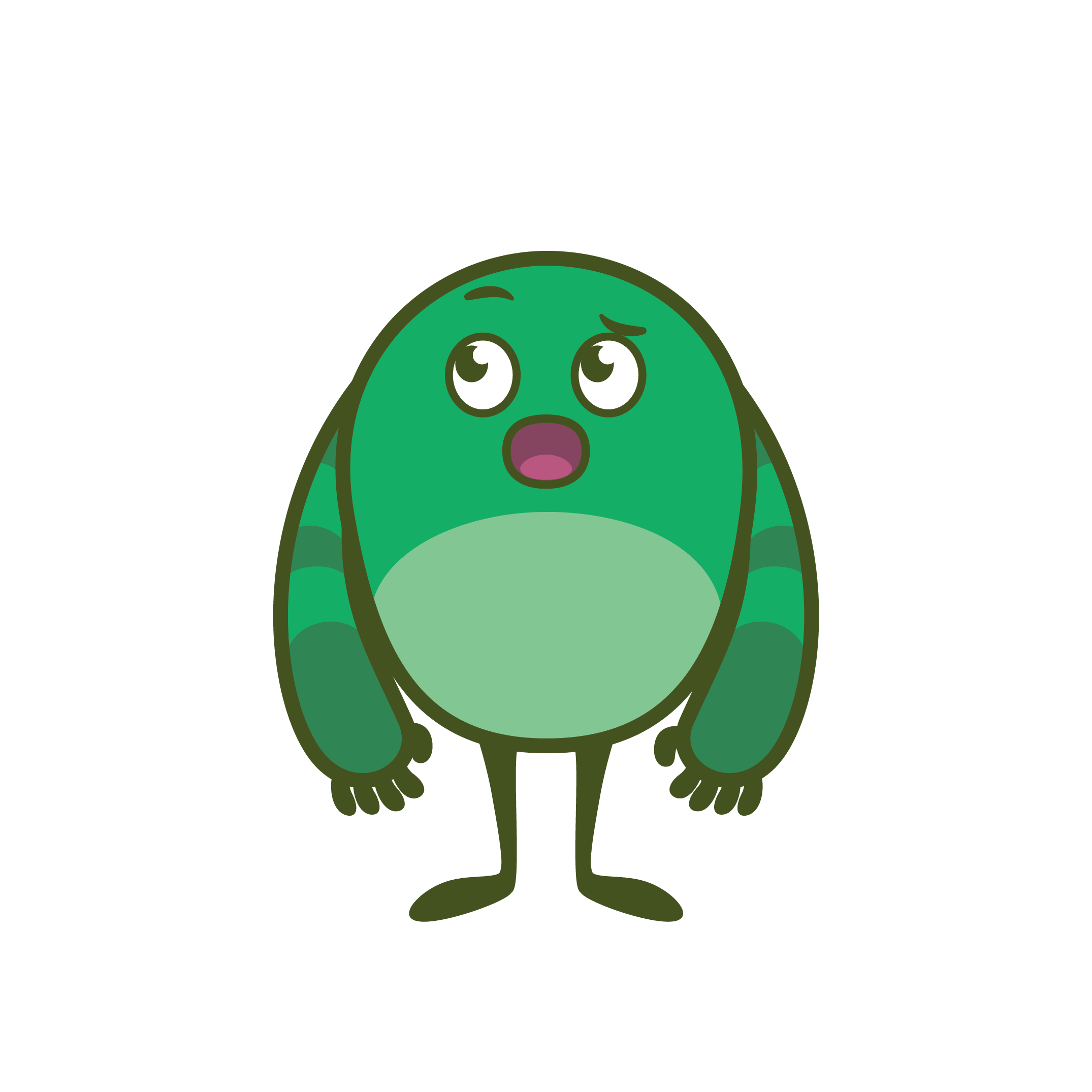
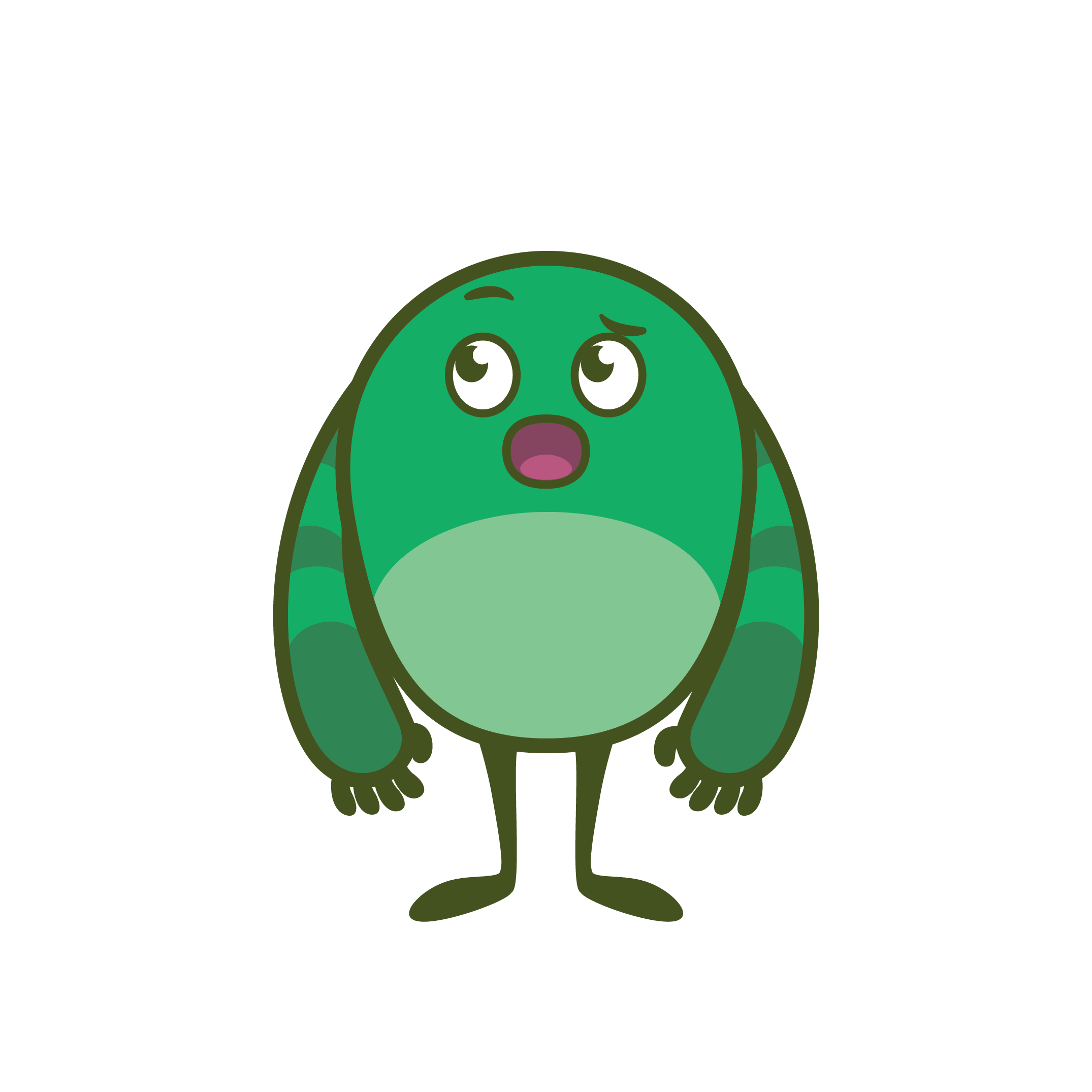
うーん…そう言われると難しい…
じゃあ、合理的配慮って?



えーっと…、分からん!
バリアフリーとは
障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。
ユニバーサルデザインとは
バリアフリー(以下BF)は、障害によりもたらされるバリア(障壁)に対処するとの考え方であるのに対し、ユニバーサルデザイン(以下UD)はあらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。
合理的配慮とは
障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
障害者一人一人に合った配慮を提供し、提供する側は法的義務があるため、合理的配慮ができる準備をしなければならない。
| 対象者 | 対応時期 | 特徴 | |
|---|---|---|---|
| ユニバーサルデザイン | 全員 | 事前的 (設計、構想) | ・デザイン性が高い ・行政対応<民間対応 ・ビフォーアフターの比較△ ・予算、費用がかかる |
| バリアフリー | 障害者 高齢者 | 事後的 | ・物理的なバリアの除去 ・行政対応>民間対応 ・ビフォーアフターの比較◎ ・デザイン性<実用性 |
| 合理的配慮 | 障害者(個人) | いつでも | ・障害者個人に対応 ・事業者の提供は法的義務 ・配慮内容の周知に課題 |



表にすると分かりやすいね!
ジェンダーレストイレ問題
歌舞伎町にオープンした「ジェンダーレストイレ」をご存知でしょうか。性別に関係なく利用できるトイレであり、世界的に広まりつつある新しいトイレの形です。いわば、「多様性トイレ」というところでしょうか。
ですが、オープンしてまもなく利用者からの不満が相次ぎ、現在は通常のトイレの形式になり、事実上の廃止となりました。考えてみると、用を足したあとに異性が同じ空間にいることは利用者にとって恐怖かもしれないです。
海外の動画がジェンダーレストイレの理想と現実を面白く表現していました。2017年の動画でした。
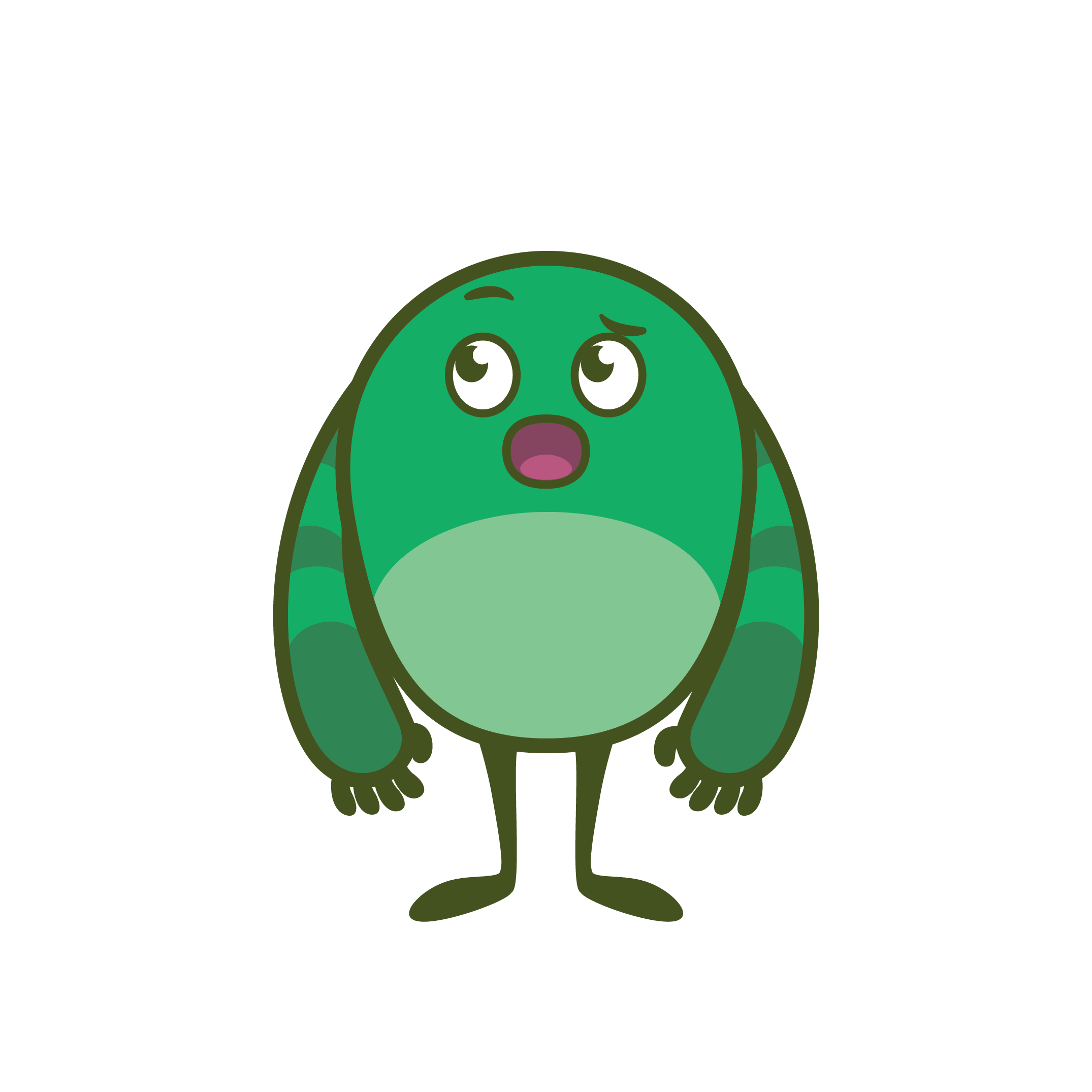
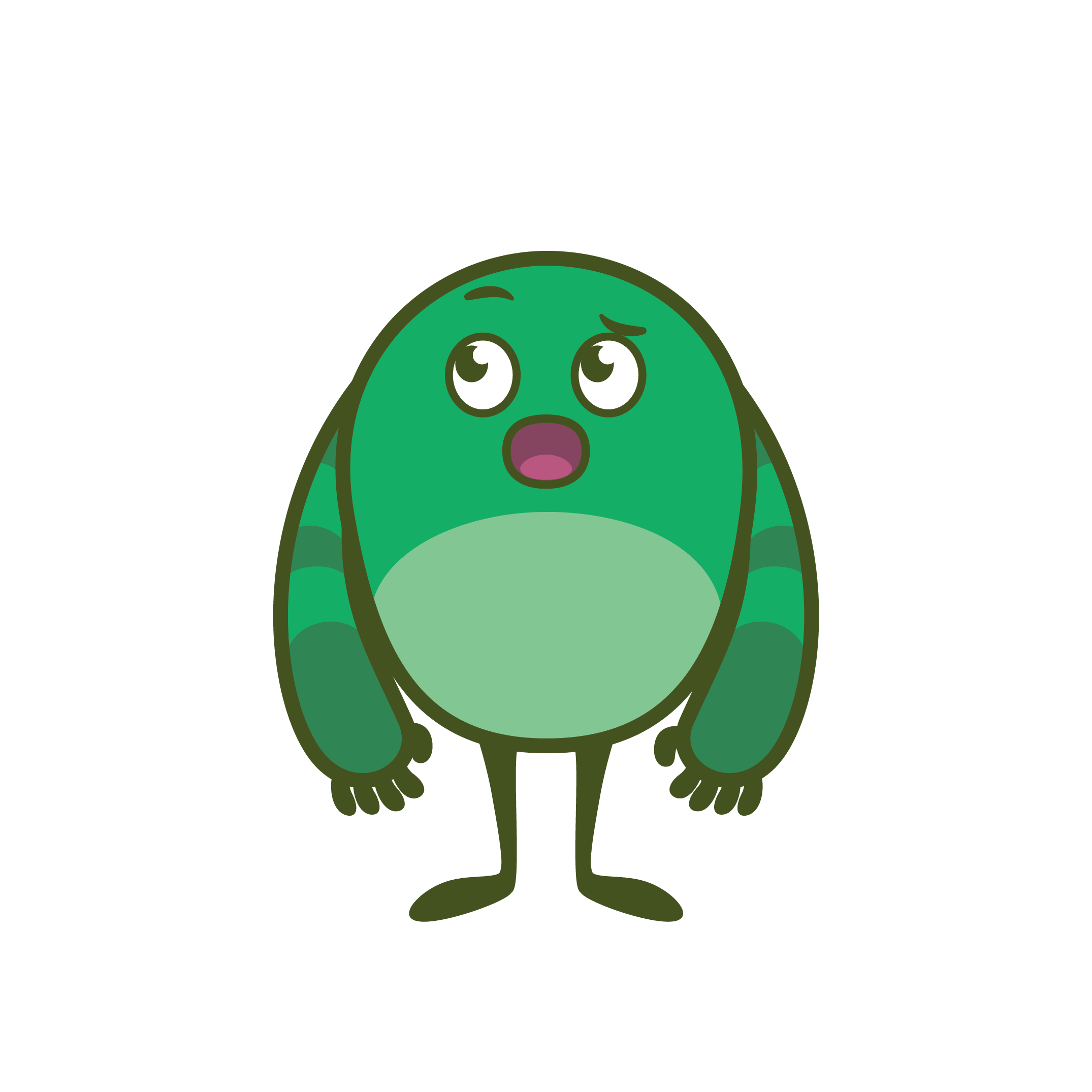
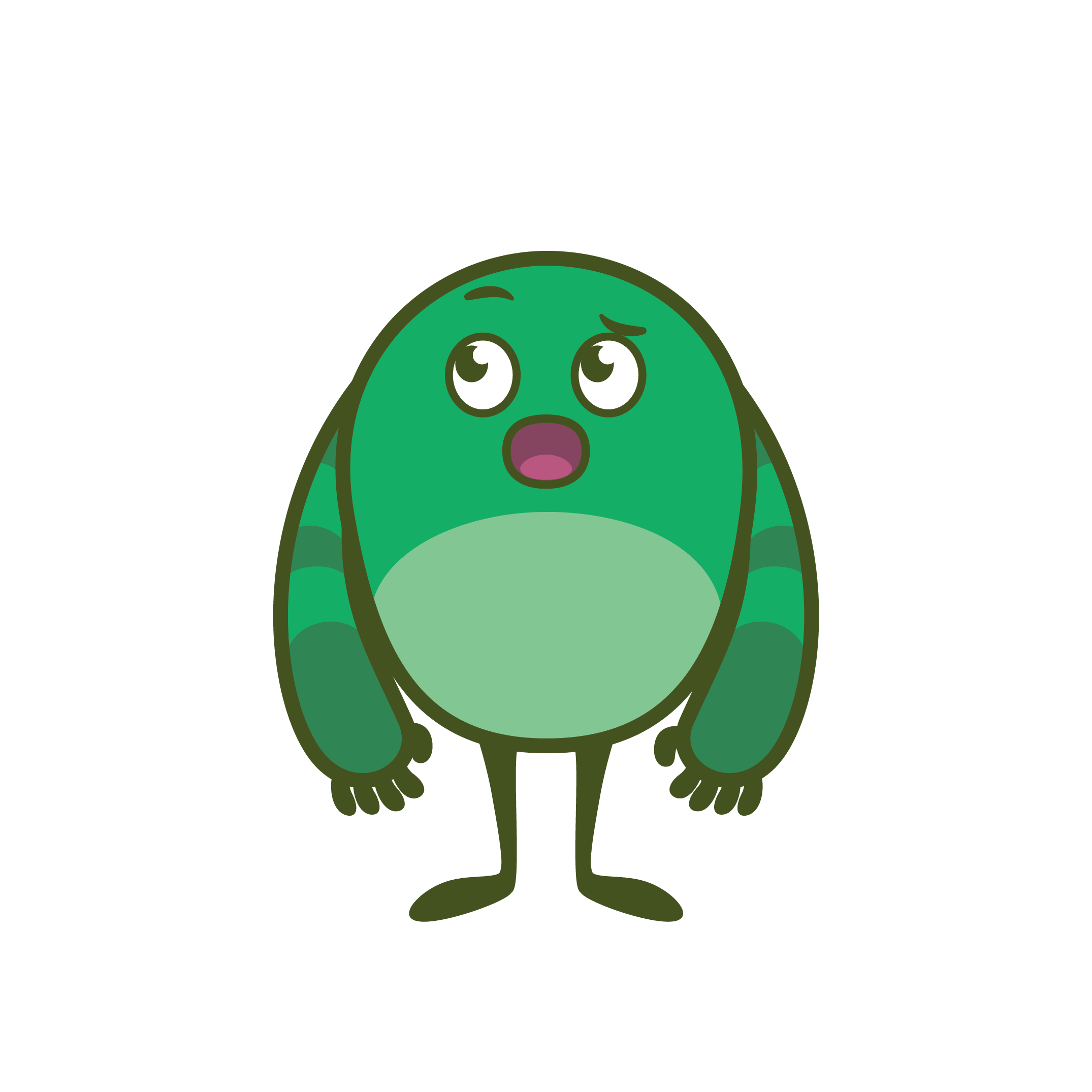
そりゃ、そうなるよね笑
エビデンスの解説
国土交通省.ユニバーサルデザインの推進
国土交通省は、全国の市町村を対象にUDの推進状況について調査した。UDの課題として、以下の点をあげました。
UD化しても、顕著な効果が分かりづらい
事前措置のため、ビフォーアフターのビフォーがない。一方、BFは分かりやすい。
UDの重要性を説明しづらい
UDのニーズは少ない?担当者の知識不足?行政と利用者のコミュニケーション不足?
UDよりも耐震化・老朽化対策の方が優先
喫緊の課題ではない?予算的な問題で後回し。
UD担当者の理解が不足
高い専門性とデザインセンスが必要か。デザイナーや建築家が携わることが多い。
本来であれば、行政が主導となって推進するべきですが、なかなかハードルが高いようです。
トクシルの考え
多機能ではなく個別最適化
例を挙げてみましょう。
例)多言語翻訳による読者層の拡大を目指す場合、以下の選択肢があると思います。
- 1冊にまとめた結果、かなり厚く重い本になりました。
- 言語ごとに別々の本にしてまとめた結果、10冊になりました。
この2つの選択肢のうち、どちらが「読者」にとってより読みやすいでしょうか。
同じ目的でもその達成方法や立場によって扱いやすさは異なります。管理者にとっては1冊の方が管理しやすい一方、読者にとっては別々の方が読みやすいです。多言語翻訳による読者層の拡大というゴールは同じでも、利用者目線で達成できる方法を選択する必要があります。
ジェンダーレストイレも同様に、トイレが1か所に集まることで掃除が楽になるという面ではメリットがあるでしょう。しかし、元々分散していたトイレが1か所に集まったことで以前よりも行列や待ち時間が発生する可能性を考える必要があります。
つまり、多様性を1か所で完全に提供しようとする「多機能型UD」は多様性の押し付けと捉えられてもおかしくないということです。そうではなく、多様性を複数の箇所で提供しようとする「個別最適型UD」にすることが、多様なニーズに適しているかもしれません。
他のブログでも同様の点について指摘しており、この点についてはトクシルも同意見です。


また、スポーツ観戦施設の座席を例にすると、
- 座席間隔が広い車イスユーザーや親子連れに適した座席
- 音や迫力が間近で感じることができる視覚障害者や聴覚障害者に適した座席
- トイレ付近や入口付近といった場所の分かりやすさを重視した高齢者や知的障害者に゙適した座席
などが「個別最適型UD」の形と考えます。



利用者第一のUDが広まるといいね!
- ユニバーサルデザイン・バリアフリー・合理的配慮の違い
- 行政の政策において、ユニバーサルデザインよりも耐震化・老朽化への対策の方が優先度が高いこと。
- 多様性を複数箇所で実現する個別最適型ユニバーサルデザインの方が利用しやすいこと。