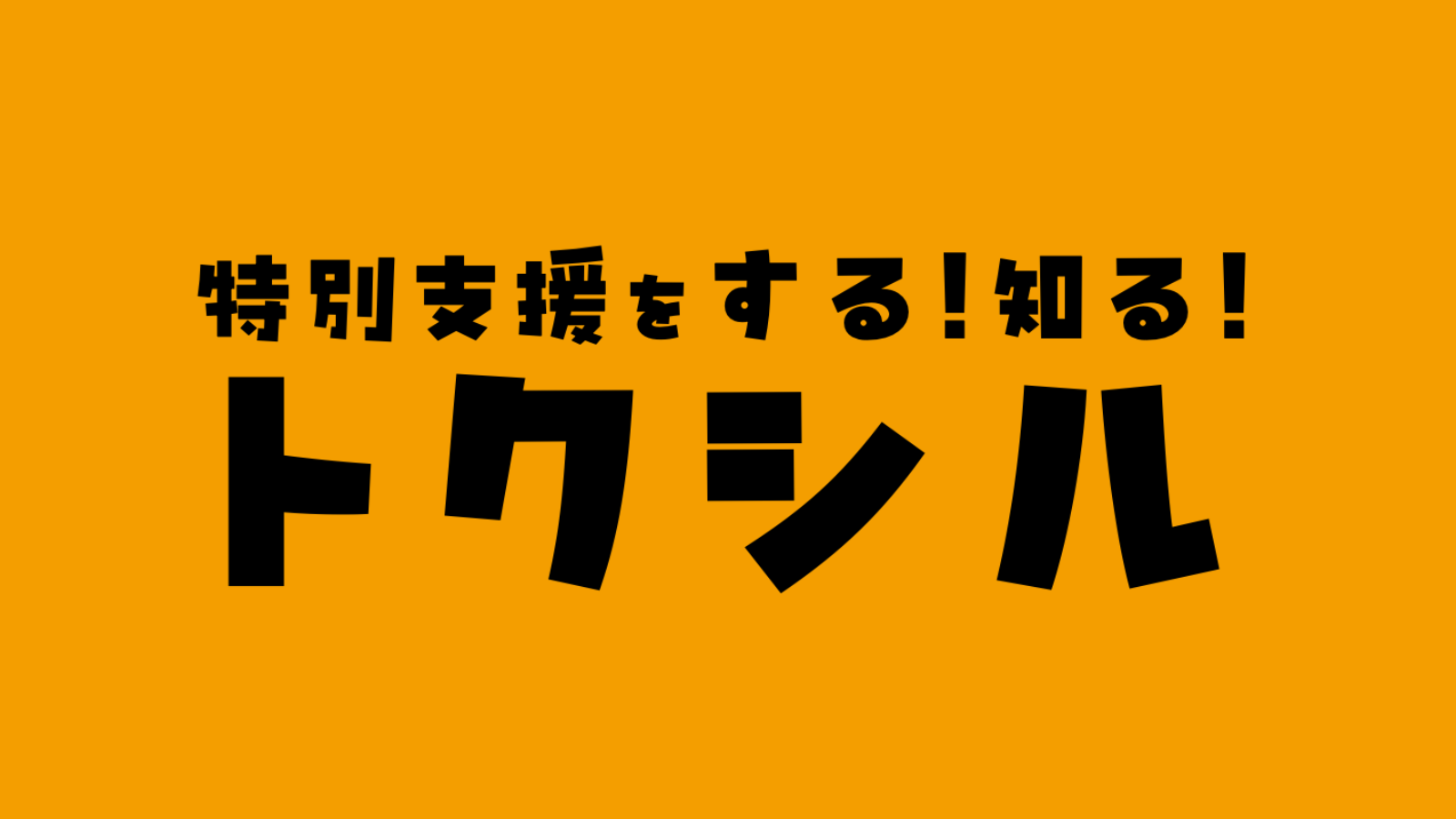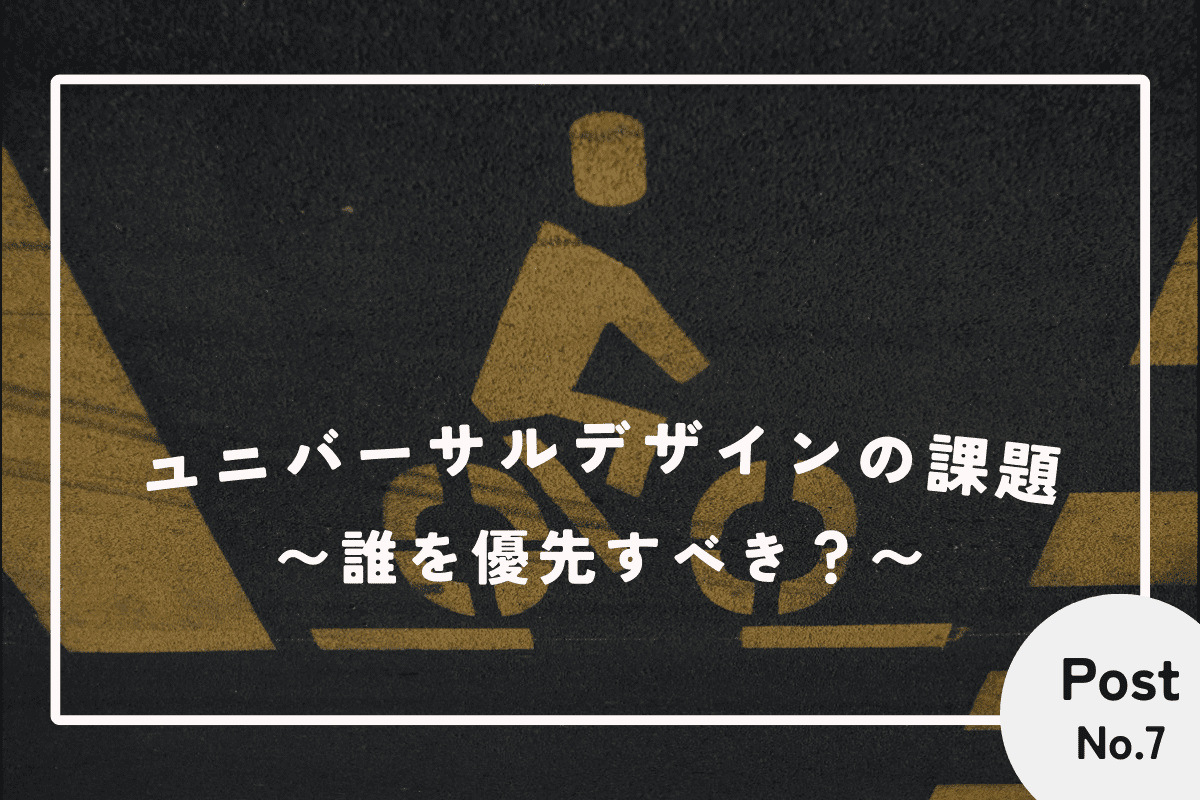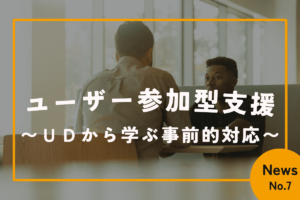ユーザー参加型支援
〜UDから学ぶ事前的対応〜
タイパ重視は
ここだけチェック!!
ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は7月13日、アクセシビリティ専門家の意見を取り入れて開発したPlayStation 5向け新型コントローラー「Access コントローラー」を12月9日に世界で発売すると発表した。国内価格は1万2980円。7月21日から予約受付を始める。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2307/14/news117.html
ニュースの解説
ユニバーサルデザインのイメージ
今回のニュースは、アクセシビリティに関するユニバーサルデザインの進展を取り上げています。具体的には、PCやゲームの環境に対するユニバーサルデザインに焦点を当てています。ユニバーサルデザインの基本的な知識については、過去の記事をご覧ください。
一般的に認知されているユニバーサルデザインは、公共施設や生活必需品に多く見られています。

https://www.kao.com/jp/corporate/research-development/fundamental/human-science/universal-design-containers/

https://whill.inc/jp/column/14_universaldesign
こうしたユーザーの悩みに対応するための“事後”的なユニバーサルデザインも決して悪いわけではありませんが、ユニバーサルデザインの原則としては、“事前”的な対応が本来求められています。
固定観念を疑う
かつては娯楽としての側面が強かったPCやゲームですが、今ではさまざまな目的に活用されるツールとして確立されています。
- eスポーツといった「競技」としての運用
- プロゲーマーや副業といった「仕事」としての運用
- 実況動画やネット配信といった「自己表現」としての運用
- オンラインの交流や会議といった「コミュニケーション」としての運用
- ゲーム治療やオンライン診断といった「ヘルスツール」としての運用
- サブスク配信や4Kの視聴といった「趣味や鑑賞」としての運用
また、教育として力を入れている専門学校もあり、PCやゲームは昔とは全く異なる立ち位置になっています。
しかし、今回のニュースを考えると、もっと早くユニバーサルデザイン化が出来ていた可能性もありますよね。新しいコントローラーもそこまで難しい技術とは思えません。ファミコンが発売されたのが40年前であるため、果たしてコントローラのユニバーサルデザイン化に至るまで40年必要だったのかを考えると疑問に感じます。
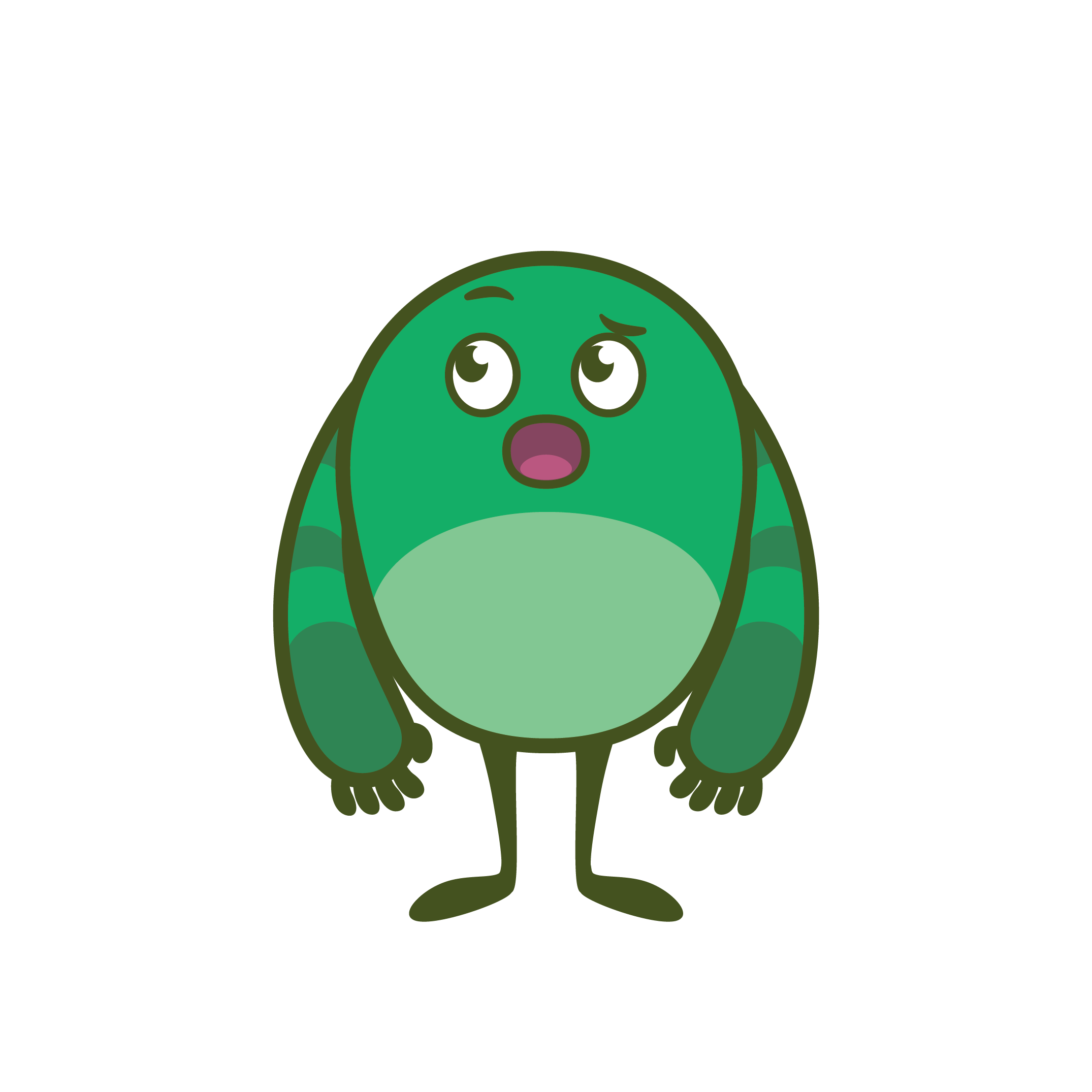 トクシル
トクシルまぁ、色々ありますから



このコントローラーの形…障害のある人は操作しにくいかも。



今後PCやゲームの進化に合わせて、発生するニーズはなにか。
こうした意識がユニバーサルデザインのアイデアを生むと考えます。この技術が20年前に出来ていたら、障害者がもっと社会進出していた可能性も考えられますよね。
つまり、ニーズが発生してから対応する”事後”的対応よりも、ニーズが発生する前に対応する”事前”的対応の方が可能性を秘めているということです。
事前対応は失敗する可能性大?
ニーズが発生する前に対応することが、必ずしも成功に結びつくわけではありません。逆に、ニーズが発生した後に対応することは、成功する可能性は比較的高いでしょう。しかし、失敗から得られる情報もあるため、最初から100点を求めず、ユーザーからのフィードバックを受けながら改良を繰り返すことも成功する方法の1つだと考えます。
トクシルとしては、これを「ユーザー参加型のユニバーサルデザイン」と勝手ながら呼ばせていただきます笑。
支援に活用できる考え方
このニュースから得られる特別支援に役立つアプローチは以下の通りです
- 様々な事例から当事者のニーズを学ぶこと
- ニーズが発生する可能性を意識し、適切な対応策を検討すること
- 当事者と一緒に支援方法を検討し、改良を重ねること
こうした「事前的対応を意識したユーザー参加型支援」は失敗が多いかもしれませんが、その分大きな可能性を秘めていると考えます。
失敗しながら改良し続ければ、よい支援に結びつくはずです。